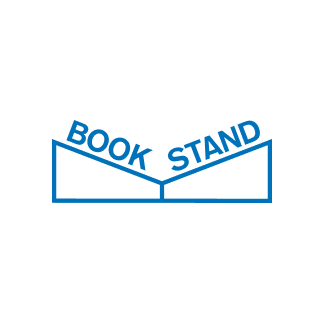美術作品との出会いは、人と同じく一期一会。美術作品は、それぞれの人間の波乱に富んだ人生のなかで、出会う時期によっては多少の意味を持ち、心の明暗に寄り添ってくれる存在――そう述べるのは、美術史家の宮下規久朗さんです。
宮下さんは自著『美術の誘惑』の中で、25のトピックを設けながら美術作品の数々を紹介。美術がどのように人びとを魅了し、寄り添う存在であったのかに迫ります。
たとえば、25のトピックのうちのひとつは「子供の肖像」。子供という概念は、遥か昔からあったもののように思いがちですが、意外にも近世になってから登場したものなのだとか。
「フランスの歴史家・アリエスの名著『〈子供〉の誕生』によれば、中世には子供という概念はなく、言葉で意思疎通できるようになる七、八歳くらいで早くも成人として扱われて労働に出され、それ以前の子供は家畜と同然のようにみなされた。一七世紀頃から大人と異なる子供という枠組みが現れ、同時に学校教育制度ができたのである」(本書より)
そのため、美術においても、子供の肖像が描かれるようになるのは17世紀頃から。親が、息子や娘の愛らしい姿をとどめたいと思い、画家に注文したのだそうです。その際、注文を受けた画家は、実物の子よりもやや理想化して描き、周囲には子供の純真さを象徴する事物を配することが多かったのだといいます。
こうした子供の肖像ですが、日本においては、戦国時代から桃山時代にかけて登場。しかし、生前の子供が描かれるようになるのは、明治以降。それまでは、子供が亡くなったときに、近親者が描かせたものが多かったといいます。
続いて宮下さんが注目するのは、「巨大なスケール」。「どんな美術作品も印刷や映像のような複製で簡単に見ることのできる現代では、作品の大きさのことを忘れがちである」と綴る宮下さん。美術作品にとって、その大きさは重要な要素なのだと指摘します。
では、美術史上、もっとも大きな油彩画とはどのような作品なのでしょうか。
その作品とは、縦7メートル、横24メートルにも及ぶ大作、ヴェネツィアのドゥカーレ宮殿の大評議会室にあるティントレットの「天国」。カンヴァスを壁面に貼りつけた、いわば壁画ともいうべき同作品は、キリストと聖母を中心に、無数の聖人や天使が描かれており、画面中央上部には、ヴェネツィア共和国の象徴である聖母がキリストから戴冠されている様子が描かれています。
そして、これだけの大きさの作品を描いた背景には、ある理由があったのだと宮下さんは指摘します。
「この部屋は、共和国の国会議事堂であるとともに最高裁判所でもあった。この壁画の尋常でない画面の大きさは、それが単なる装飾や芸術作品ではなく、国家の政治的機能を代弁するものであったからにほかならない」(本書より)
美術の誘惑に駆られるには、まずは作品の前にじっと立ってみることが重要だといいます。人生のさまざまな機会に美術作品に触れてみると、感じるところも多々あるかもしれません。