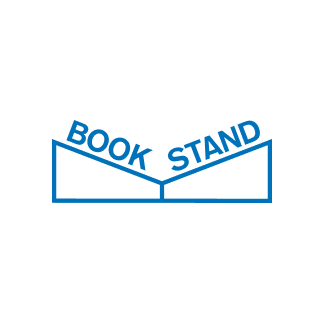もともとは児童文学として出版されながら、大人にも読まれる作品は数多く存在します。たとえば、最近では『ハリー・ポッター』シリーズがその代表例といえるでしょう。また、ジブリ映画にもなった『ハウルの動く城』シリーズや『ゲド戦記』も児童書として出版されていますし、もっと古いものでいえば『赤毛のアン』も児童文学として分類される場合が多くなっています。
今回、ご紹介する『言葉屋 言箱と言珠のひみつ』も、「大人にも読まれる児童文学」となりそうな予感のある作品。
主人公は、小学5年生の女の子、古都村詠子。彼女のおばあちゃんは、表の顔は雑貨屋ながら、その実、言葉に関する勇気を提供するお店「言葉屋」を営む人物です。詠子ははじめ、おばあちゃんが言葉屋として何をしているのか知らなかったものの、強い興味を持ったことから言葉屋の工房を思わず覗いてしまいます。結果的に、おばあちゃんにバレてしまいますが、このできごとをきっかけとして、詠子も言葉屋の修行をするように。詠子が言葉と人、人と人との関係について考える日々が始まります―――。
同書が、大人でも楽しめる作品である理由はいくつかあります。
第一に、言葉屋という仕事が生まれた背景が実に「凝っている」点。時は15世紀、ヨハネス・グーテンベルクが活版印刷を発明したころに遡ります。印刷技術の確立により、それまでよりも多くの人の手に本が行き渡るようになりましたが、特に書物が集中したのは「水の都」ヴェネツィア。かの地は交易都市であり、なおかつ、ルネサンス期と重なり数々の天才たちが集まったことで、世界中の情報(=本)が集積する街となりました......ここまでは史実どおりの話です。
一方で、ヴェネツィアン・グラスでも知られるように、ヴェネツィアはガラスの街でもあります。そして、16世紀に生きた1人のガラス職人が、本になることを認められずに捨てられてしまった言葉があまりにも多いのを哀れに思い、言葉をしまっておく「言箱(コトバコ)」をつくった、というのを言葉屋の始まりとしています。史実とファンタジーを織り交ぜた設定は、子どもでも大人でもリアリティを感じられるのではないでしょうか。
実際に本書を読んだ大人の中には、小学生が「由緒正しい」という言葉を発したり、情景描写にある「四肢を駆け抜けた」といった表現は「子どもにはわかりづらいのではないか?」と感じる人もいるかもしれません。ただ、大人がときに「子どものころに戻れたら」と思うのと同様に、子どもは「早く大人になりたい」と思うもの。本書はもともと『朝日小学生新聞』の連載小説として人気を博し、「第5回朝日学生新聞社児童文学賞」を受賞しましたが、こうした「背伸びした感じ」が子どもに受け、そして大人が読むにも耐えうる小説に仕上がった理由といえそうです。
ストーリーは、主人公の詠子が小学6年生に上がる直前で終わります。言葉屋としての修行も、おそらくはまだまだ序の口の段階であることを想像できますが、ぜひ続編が制作され、彼女がどのように成長していくのか、読んでみたいと感じる一作です。