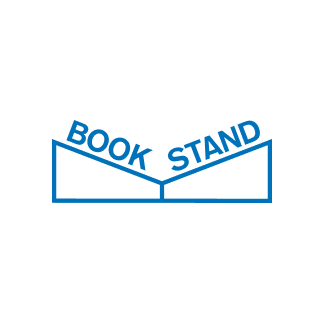『食堂かたつむり』や『つるかめ助産院』など、作品が次々と映像化され、その名が広く知られている小川糸(おがわ・いと)さん。新刊『リボン』は一羽のオカメインコ・リボンを軸に、リボンと触れ合う人の様々な人生が描かれた一冊。併せて出版された『つばさのおくりもの』ではリボンの視点から物語がつづられており、作品を違った視点からも楽しめるようになっています。実は今回の作品、構想は代表作のひとつである『食堂かたつむり』の刊行準備中の頃からあったといいます。
ずっと一羽の鳥が人をつなぐ物語を書きたいなと思っていたんです。構想は7~8年前、『食堂かたつむり』の刊行が決まった頃からありました。『リボン』も書きたいなと思いつつ、タイミングが合わず、今回出版することになりました。
――『リボン』ではどんなことを描きたかったのでしょうか。
人と人とがつながっていく物語が書きたいな、と。作品の中でリボン自身は、誰かを勇気づけようとか、励まそうとか意識しているわけではないですけれども、結果としてそのまわりの人が癒されたり、慰められたりしているんです。人も同じように、意識的に「頑張って」とか伝えなくても、それぞれがいるだけで、リボンの役割を果たしているのかなということを感じていただけたらと思います。
――今回は『リボン』と併せて『つばさのおくりもの』という、リボン目線での短編も出版されていますが、この構想も当初からあったのでしょうか。
『つばさのおくりもの』は、毎日新聞の関西版に連載していたものなんですが、その依頼があったのが、ちょうど『リボン』を描いていたときだったので、リボン自身の視点も描いてみたいなと思って。最初は一冊の本の中に収めようと思ったんですけど、読む人が混乱してしまうかもしれないというのと、あくまで『リボン』は小説として読んでもらいたいというのもあって、別の本として出すことになりました。『つばさ...』の方を後に書いているので、『リボン』で描いていない空白の部分が書けたらいいな、と思って書きました。
――作品の中では、おばあちゃんの「すみれちゃん」とその孫の小学生「ヒバリさん」の間柄が、とても仲良く、友達関係のように描かれていますが、小川さんご自身にも通じるところがあったんでしょうか。
私も家族の中で、一番長く時間を過ごしたのは祖母でしたし、布団を並べて眠ったりもしていました。私も祖母と一緒にインコを飼っていたんです。私は残念ながら途中で逃がしてしまったこともあったのですが、その分、小説の中では長生きさせてあげたいなと思って書きました。
――作品の中でのヒバリさんはおばあちゃん子で、リボンに夢中な鳥好きの女の子ですが、小川さんご自身は小さい頃はどんな女の子だったんですか?
割とインドアな子で、学校帰りに図書館に寄ったりしていました。小学校では1年生から6年生まで、毎日日記を書いて先生に提出してコメントをもらう、っていうのが宿題だったのですが、その日記を書くのがすごく好きだったんです。読んでもらえて、コメントをもらえる、っていうのがすごくうれしくて。みんなは「今日はこんなことがあって...」というのを書いていたんですが、当時の私は詩を書いたり、物語のようなものを書いたりしていました。今も2~3冊くらい残っているんですよ。宝物ですね。
――それはすごく貴重な日記ですね。書いた内容で、覚えているものはありますか?
運動会の日に書いた日記があるのですが、それが競技とか、運動会については全く触れていなくて、その日の朝の、空についてひたすら書いたものだったんです。ちょっとズレてますよね(笑)。「なんでその日は雨が降ったのか」とか、「空では何が行われていたのか」とか、全然、運動会じゃないんですよ。そうしたら先生はすごく心配してくれて「この子大丈夫かな」って(笑)。その日の先生のコメントには「それで運動会はどうなったの?」って書いてありました(笑)。
――小学生のころから独特の視点を持っていたんですね(笑)。作中にはドイツについて書かれている部分がありますが、これは実際に行かれたんでしょうか。
はい。以前ドイツに行ったときにすごく気持ちのいい街で、これはゆっくり滞在しないと良さが分からないな、と思ったんです。そこで一昨年と去年、2~3カ月滞在したんですが、そうしたらますます好きになりました。また、私が滞在したアパートがたまたまベルリンの壁に近かったんです。かつて東と西とで分かれていたところを、私は毎日、横断歩道で渡りながら、昔はここが渡れなくて命を落とした人もいたんだな、と思ったり。人々の暮らしを分断していた壁の存在を肌で感じることができました。
――長期のドイツ滞在でしたが、それによって変わったことなどはありましたか?
仕事に関しての考え方に、影響を受けました。「振れ幅」ってすごく大事だなって思うんですけど、ベルリンの人の考え方はまさにそうで、「遊ぶ時は遊ぶ、働くときはしっかり働く」っていうのが、すごくきっちりしているんですね。これはドイツの人ではなく、『つるかめ助産院』を書いていたときに聞いた、助産師さんの言葉なんですが「ゆるんでいないと、いざという時に力が入らない」っていう言葉があって。ずっと力が入っていたら、いざっていうときも力が入らなくて、子供が産めないでしょ?って。ゆるんで、力んで、ゆるんで、力んで、っていうのがないといけない。ずっと力んで、ある程度は続けて仕事ができても、そのあと体に負担がかかって続かなかったりして、フタをあけるとマイナスになったりということもあります。ドイツでの滞在やこれまでの経験を経て、長編5作目の今回で、自分が一番いいペースというのがだいぶ分かってきました。
『つるかめ助産院』で妊婦さんに取材をしたときに、「3人目でようやく理想の出産ができた」という話を聞いたという小川さん。当時はその意味がよくわからなかったそうですが、今作の出版でわかるようになったといいます。陣痛促進剤などを使わず、陣痛の波に乗って産むことが「気持ちいいこと」だと話した妊婦さんのように、何かに急かされたりすることなく、自分のペースの波に乗りながら作品を生み出すことで、自分の心持ちも良くなるのだと感じたそう。小川さん自身にも大きな影響を与えた『リボン』と『つばさのおくりもの』。ファンならずとも手に取ってみたくなる一冊です。
■小川糸(おがわ・いと)
1973年生まれ。2008年に『食堂かたつむり』を発表、ベストセラーとなり映画化され、広くその名を知られる。2010年には小説『つるかめ助産院』がNHKでドラマ化された。その他著書に『喋々喃々』『ファミリーツリー』『あつあつを召し上がれ』『さようなら、私』などがある。