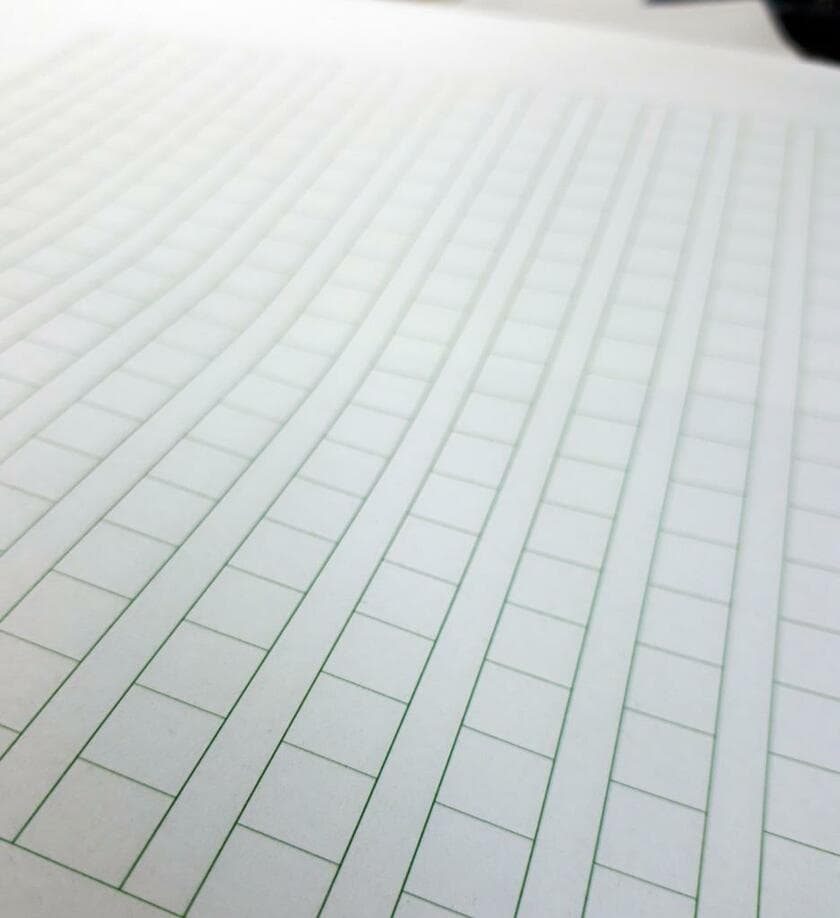
書評家の倉本さおり氏が選んだ“今週の一冊”は『あちらにいる鬼』(井上荒野著、朝日新聞出版※1,600円※税別)。
* * *
書店ではじめて本書の存在を知った読者は、まずは帯に並んだ文言に釘付けになるにちがいない。
<作者の父井上光晴と、私の不倫が始まった時、作者は五歳だった>
推薦文を寄せたのは瀬戸内晴美(現・寂聴)その人。本書は井上の娘である井上荒野が、彼の妻──すなわち自身の母親と瀬戸内をモデルにした女性二人の視点から、そこにあった情交を微に入り細を穿ちながら描き出したものだ。
なるほど、その一文は実にスキャンダラスで、ともすれば挑戦的な響きすら漂う。だが数ページも読めば、当初想像した場所よりもずっと静かで深い場所に連れて行かれていることに気づくはずだ。そして瀬戸内が、このような形で最大限の賛辞を贈った意味もわかってくる。
1966年、春。人気作家の長内みはるは、気鋭の純文学作家・白木篤郎と講演旅行で同席する。初対面なのにやたらとずうずうしく、傲慢な態度を見せたかと思えば無防備に感情を晒す篤郎。そのふるまいに振り回されながら、みはるはすでに自分が目の前の男に惹かれていることに気づいてもいる。
一方、篤郎の妻・笙子は、ほとんど野放図ともいえる夫の女性関係に煩わされながら、結果的に黙認する形で生活の平穏を保ってきた。むろん篤郎とみはるとの出会いの中に何かあったことにも当然のように勘づいている──というより、奇妙なことに篤郎自身がそうなるように仕向けているふしさえあるのだ。ほどなくして篤郎とみはるは実際に関係を持ち始めるが、笙子はこれまでとは異なる言い知れない気配を感じ、とまどいを覚えながらも興味をひかれていく。
そこにあるのは「不倫」という言葉にありがちな、ひとりの男を奪い合う構図ではない。いうなれば、<わたしの男>から<わたしたちの男>へと変貌していく過程だ。物語が進むにつれ、みはると笙子は篤郎という男を通じて互いの姿を透かし見るようになる。
だが「特別な関係」という、どこか収まりのよい常套句もまたふさわしくない気がする。なぜなら本作は、そんなふうにして体よく「」に括られたものの中身をすっかり露わにしてしまう小説でもあるからだ。
関係が始まってしばらくすると、みはるは篤郎に作品を添削してもらうようになる。<自分の文章のある部分を、彼の赤い線が強く否定しているのを見たとき、見せてはいけない体の一部分を見せてしまったかのように、顔が赤らむ思いがした>──なんとエロティックな場面であることか。みはるにとってその時間は<もう一種類の性交のようなもの>であり、だからこそ自分と他の女との違いを自覚してもいる。笙子がみはるを「特別」と感じる理由もそのことと無関係ではない。
けれど、実は笙子もまた、篤郎の名義で小説を書いていたことが読者の前に明かされるのだ。つまりみはるが「篤郎」だと思っているものの中には「笙子」自身がそのまんま混ざり込んでいるということになる。
嘘がどのくらい混じっていようが、小説というのはどうしようもなく、書いたひとの中身なのだろう。
やがて篤郎の熱は他の女へと気まぐれに移っていく。失望と諦念。それでもゼロにはできない自らの情念。みはるは出家し、書き続けることを選ぶが、笙子は書くことを放棄し、篤郎の妻であり続ける。
業、というものを突きつけられる小説だ。一分の隙もなく選び抜かれた言葉から、おそろしく解像度の高い情景が浮かび上がる。
恋愛とはある種の治外法権であるということを、かつて私は瀬戸内晴美の小説から学んだ。けれど井上荒野の小説は、そのこととまったく矛盾しない形で彼女たちの守っているものを丸裸にしてみせた。ほんとうに、すごいものを読まされてしまった。
※週刊朝日 2019年4月12日号






















