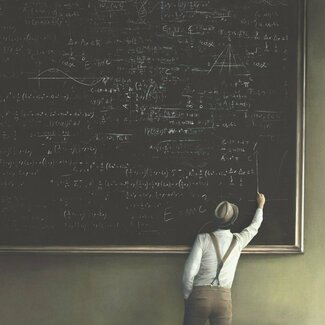当時、新人研修は築地の電通別館13階でおこなわれ、夕方5時までがいわゆる座学。第20班の8人はそれが終わると、鬼が待つ聖路加タワーの本社9階に向かって階段を駆け降りる。
新人は全員、エレベーター使用が許されない。機転のきく新人は、研修2日目から走りやすいクツを用意していた。
本社に着くと8人は鬼の周りに立ち、電話番をする。モタモタすれば、カミナリが落ちる。内線電話は鳴る前に光ることを知った新人は、仲間から一目置かれた。
夜7時を過ぎると、リーダーの「そろそろいくぞ」の一声で、銀座に向かう。腹ごしらえをすませ、バーをはしごしながら夜の研修が始まる。
「俺たちは銀座しばりだ」が鬼の口癖の一つだった。飲食は原則、銀座以外ではしないという意味である。リーダーの後を小走りで追う新入社員の姿は、カルガモのヒナのようだった。
夜の研修で、後輩や新人に対しては「バカヤロー」を挨拶代わりにする柴田は、言葉使いから箸の上げ下ろしにいたるまで、教えるというより、叱り続けた。
そして、
「広告代理店というのはな、会社と会社、人と人の間に立ってつなぐのが仕事だ。どんな時も、当事者意識を持て。自分ならどうするか、考える癖をつけろ。何があっても『Be there』だ。そこにとどまれ。逃げるな。いいか」
と言い続けた。
研修中の大安前日の夜のこと。柴田が講師役を頼んだ仕事先の会社の中堅社員がきていた。午前零時が近くなり、「明日は友だちの結婚式なので、家に帰って礼服に着替えたいのでお先に失礼します」と言う新入社員に柴田は、「礼服は明日、俺が買ってやる。帰るな」と言った。そして翌日、その通りにした。
この時期、彼は電通新聞局の朝日新聞担当チームのキャップでもあった。10人近い部下を持ち、若い部下には、
「お前は、朝日に電通ファンを作ることが仕事だ」
と言い、毎朝、社説や天声人語についての意見、感想を言わせた。
彼を見送る人波の中に朝日新聞社広告局長、上田周がいた。彼は桜の一枝を手に、気が付くと柴田の後に続いていた。
現在「朝日広告社」(北九州市)社長の上田は言う。
「柴ちゃんは朝日に来る時も、シルバーのアタッシェケースなんです。仕事もできたけど、見た目にもカッコよかったんですよ」
広告局長と並んで広告第3部長、酒徳彰の姿もあった。現在、大阪本社の広告局長補佐の酒徳は当時を振り返って、
「電通の朝日担当とは何人も付き合いましたけど、柴ちゃんは体育会系軍団の最強のリーダーですね」
と言った。
入社の時から柴田を知る電通マンの先輩、岡本久暢・元文教大学非常勤講師は、次のように話している。
「一言で言うと、彼は誠実な仕事師ですよ。難点は目立ちすぎたことかな。しかし、朝日新聞社をサッカー・ワールドカップのオフィシャルサプライヤーにしたのは、彼の大きな功績でしょう。何しろ、読売新聞の渡辺恒雄さんに地団駄を踏ませたんですから」
『ビジネスで活かす電通「鬼十則」』はそういう元電通マンが、23年間で得た知識と知恵を詰め込んだ一冊である。"闘い"の記録でもある。
ゆとり教育世代に頭を痛める会社が多い現在、参考になる体験談もある。
たとえばこういう話だ。
電通に入社して何年もしない後輩と、企画を相談していた時だ。「どこに出しても恥ずかしくなくて、提案と同時に完売する企画を考えます」と言う後輩に、
「そんなことを考えていたら、お前、定年になっちまうぞ」
と叱った話などだ。
現在、友人と人材開発や企業・団体の広報・宣伝のコンサルタント会社を作った柴田は、執筆の動機をこう話している。
「人は誉めて育てろと言いますが、本当にそうでしょうか。本気で育てようと思ったら、心を鬼にして叱り続けることだと思います。叱ることの大切さ、大変さは、いずれ部下を持てば、わかることですから」
著者とつながりの深かった会社7社の現職幹部がそれぞれに十則の活用法を語っている。これも本書の魅力だ。 (川村二郎)
*
しばた・あきひこ 1959年9月、東京都生まれ。慶大卒。83年電通に入社、新聞局業務推進部長などを歴任した
*
かわむら・じろう 1941年、東京都生まれ。慶大卒。元「週刊朝日」編集長。文筆家。主な著書は『炎の作文塾』『いまなぜ白洲正子なのか』『学はあってもバカはバカ』