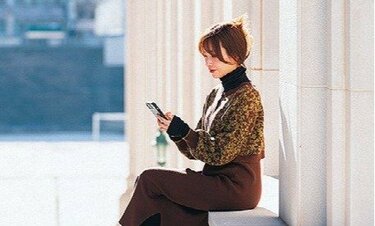この時季になると、テレビで怪談番組が放送されたり、お化け屋敷が大盛況だったり、夏=怪談というイメージが定着しています。 すでに江戸時代・中後期には、「夏の怪談」が庶民の間で流行し…
続きを読む
訪問介護の基本報酬減額は「問題だらけ」 上野千鶴子さん「国が言わない引き下げの狙い」指摘
この時季になると、テレビで怪談番組が放送されたり、お化け屋敷が大盛況だったり、夏=怪談というイメージが定着しています。 すでに江戸時代・中後期には、「夏の怪談」が庶民の間で流行し…
続きを読む