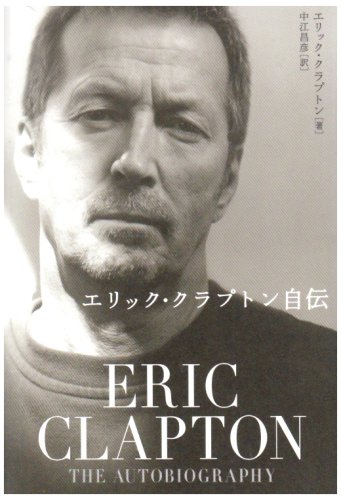すでに何度か書いてきたことだが、1974年の春以降、エリック・クラプトンは、オクラホマ州出身のベース奏者カール・レイドルを中心にしたアメリカ人バンドと活動をともにしてきた。彼らに支えられて復活をはたし、彼らとのレコーディングやツアーを通じてあらためて自信を深めた。そういってもいいだろう。
この時期、アルコールへの過度な依存が同時に進行していたことも、何度か書いてきた。自叙伝では、それが原因で多くの人たちを傷つけたとも書かれているが、おそらくその最たるものが、彼らとの決裂だった。しかもそれは、「そろそろ新しい方向性を打ち出したい」といったような、ポジティヴな発想からの動きではなかった。彼らが生み出すグルーヴ感を愛し、得がたいものと感じながらも、『モンティ・パイソン』の英国的笑いを解さない彼らにいら立ったことが直接的な原因だったらしい。
1978年11月にリリースされた『バックレス』は、結局、彼らとの最後のアルバムとなった。『サタデイ・ナイト・フィーヴァー』に起用されて大きな成功を収めたイヴォンヌ・エリマンはすでに録音前から離れていたのだが、発表後のツアーからはマーシー・レヴィが抜け、さらにはジョージ・テリーがイギリス人ながらカントリーにも精通するギタリストとして高い評価を獲得していたアルバート・リーに替わり、最終的にはカール、ジェイミー、ディックのオクラホマ組も解雇ということになってしまったのだ。
ボブ・ディランが女性シンガー、ヘレナ・スプリングスと書いた2曲を提供していたこと、外部ライターの作品ながらシングル・カットされた《プロミセス》が全米チャートでトップ10入りをはたしたこと、前作につづいてJ.J.ケイルのソングブックから《アイル・メイク・ラヴ・トゥ・ユー・エニィタイム》を取り上げていたことなど、話題は多かった。クラプトン自身も、《ウォッチ・アウト・フォー・ルーシー》や《ゴールデン・リング》など、それまでにはなかったタイプのオリジナル曲を書いている。また、カールたちに捧げたものと思われる《タルサ・タイム》という曲も収められていた。しかし、そういった微妙な時期に録音されていたこともあり、『バックレス』は、中途半端な内容の作品という印象を免れない。それは、クラプトン本人が、いちばんよくわかっていたことだろう。
アルバム『バックレス』の、愛器ブラッキーを抱えたジャケット写真は、パティ・ボイドが撮影したものだ(クレジットは、ニッネームのNELLO)。発表から4カ月後ということになる1979年の3月29日、二人は、ついに結婚式をあげている。クリーム時代の出会いから数えると、13年後のことだった。[次回1/28(水)更新予定]
 大友博
大友博