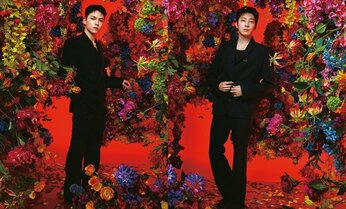姜尚中「内閣とジャニーズの改造人事 組織内権力の再分配で問題は解決しない」
姜尚中(カン・サンジュン)/東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史
政治学者の姜尚中さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、政治学的視点からアプローチします。
* * *
今回の内閣改造には何のための内閣改造なのか、そのミッションが見えてきません。内閣改造をするならば、やはりそこにある一定のビジョンがあるから改造人事をやるわけです。しかし、それがないままに党内の言わば利益分配ならぬ役職分配で、前回は大臣にありつけなかった待機組にうまく役職をロンダリングすることで「岸田内閣よろしくね」と、政権基盤を強化するために改造を強行したとも言えます。すべて政権の延命のためです。
本来の改造人事は、どんな問題を課題として設定して、そのためにどういう適材適所で人物を配置するという課題解決型でなくてはいけないはずなのに、安倍政権以降、権力の再分配による役職分配によって政権の延命を図るための内閣改造が当たり前になっているようです。
この構図は、ある意味でジャニーズ事務所も似ていると思います。先日の会見で新社長の発表がありましたが、問題の元凶の周辺にいたインサイダーたちが改革の主体になっているのですから、問題は切開されないでしょう。組織内の権力の再分配で、世論の風圧を凌ごうとする姿は、牽強付会を承知で言えば、自民党の「改革」「改造」とダブってしまいそうです。
【こちらもチェック!】
姜尚中さんのコラム「eyes」はこちら!
ジャニーズ事務所が「帝国」と呼ばれるほどに力を持つことになったのは、ここ30年の間のことだと思います。帝国が築きあげられ力を維持していく、そういう視点で比べればジャニーズ事務所の力関係は、自民党政治にも似ている部分があります。小選挙区比例代表並立制導入から同じくほぼ30年、自民党は十数年前に一旦は下野したものの、その最大の恩恵を受け、政権を維持しています。それぞれトップにカリスマがいて、長らくその首に鈴をつけられなかった、そんな状況も似ています。みんなまあまあ儲かっているからそれでいい──そんな体質が体制を許してきたのでしょう。
政治が矮小化され、時々の自分たちの利害関心だけで大きく変わっていくと、そのツケは全部国民に回されます。今回の内閣改造でいえば、誰がどんな役職に就いたのかに一喜一憂することなく、いい加減、観客民主主義から脱却していかないといけません。
◎姜尚中(カン・サンジュン)/1950年熊本市生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了後、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授などを経て、現在東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史。テレビ・新聞・雑誌などで幅広く活躍
※AERA 2023年9月25日号