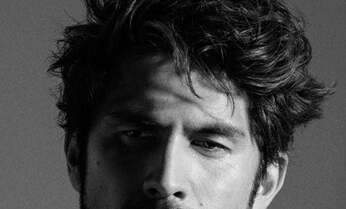【石井光太 特別寄稿】新著『43回の殺意 川崎中1男子生徒殺害事件の深層』に寄せて
ノンフィクション作家・石井光太さん。アジアの貧困街の裏側を描いた『物乞う仏陀』(文藝春秋)、『神の棄てた裸体』(新潮社)、『レンタルチャイルド』(新潮社)や、東日本大震災をテーマに被災地の知られざる真実に迫った『遺体―震災、津波の果てに』(新潮社)、さらに実の親による子殺し事件にフォーカスした『「鬼畜」の家』(新潮社)。今まで発表してきた諸作で、現実に起きた事件、さらに今私たちが生きている社会の裏側までもえぐり取るように描写してきた石井さんが、次なるテーマに選んだのが「川崎中1男子生徒殺害事件」でした。
今回、Bookstandでは、『43回の殺意 川崎中1男子生徒殺害事件の深層』(双葉社)の発刊を記念して、石井さんご本人にご寄稿いただきました。
2015年2月20日、川崎区の多摩川河川敷で中学1年の上村遼太君が、17歳~18歳の少年A、B、Cにカッターナイフで43回切りつけられて殺害されるという事件が起きた。川崎中1男子生徒殺害事件である。今回、私はこの事件の全容を『43回の殺意 川崎中1男子生徒殺害事件の深層』(双葉社)というルポにまとめた。なぜ今、この事件ルポを著したのかということについて述べたい。
この事件は、筋金入りの不良たちがか弱い中学1年生を殺害したという、いわゆる不良たちのリンチ殺害事件ではない。実は、加害少年らは、小、中学時代はいじめられて不登校にまでなっており、いわば「マイノリティー」に属するような子だったのだ。そこで見えてきたのは、今の「不可視化」された社会の縮図だった。
たとえば、主犯の少年A(事件当時18歳)は、川崎でトラック運転手をしている日本人の父親と元ホステスのフィリピン人の母親との間に生まれたハーフだった。両親は力によってAを抑えつけていたらしい。言うことを聞かないと、父親は拳どころか、足で顔面を蹴りつけたり、5時間も6時間も正座させたりした。母親もまたハンガーで殴るなどしていたそうだ。
学校でも、Aは虐げられていた。同級生から「フィリピン!」と呼ばれていじめられていたのだ。中学に進学した後は、同級生ばかりでなく、下級生の不良にまで目をつけられて不登校になった。
家にも、学校にも、居場所がなかったAは、イトーヨーカドーにあるゲームセンターに入り浸った。ここは、同じような境遇のいじめられっ子や不登校児のたまり場だった。Aはそんな人々とグループをつくり、アニメやゲームに夢中になって寂しさを紛らわせていたという。
少年B(事件当時17歳)もまた、フィリピン人ホステスの母親が未婚の男性との間に産んだハーフだった。母親はBのことを育児放棄していたばかりか、日本語をほとんどしゃべることができなかった。Bは母親が語るタガログ語を理解できず、怒鳴りつけられたり、無視されたりしていたそうだ。
そんなBもまた学校でいじめに遭い、不登校になっていく。母親はそんな息子と向き合うこともせず、家に恋人をつれ込んで同棲をはじめたり、学校側から注意を受けたという理由だけでBをフィリピンへ数カ月置き去りにしたりする。
Bは信頼できる友人さえつくることもできず、中学を卒業すると都内の通信制高校へ進学した。母親は男と別れて別の恋人を見つけて新たなマンションへ引っ越すが、Bは家の合鍵さえ持たせてもらっていなかった。
AとBは同じ川崎区の出身だったが、学年が一年ズレており、出身中学もちがった。二人が友人を介して出会うのは、高校に入ってからだ。
Aはゲームセンターで知り合った不登校やいじめられていた少年たちとグループをつくっていた。大半が事情を抱えた家庭の子で、定時制高校か、通信制高校、あるいはフリーターだった。そこにBが交ざるようになるのだ。みんな、アニメとゲームでつながっている「オタク」っぽい子供たちだった。
事件の一年ほど前、このグループに新たに加わったのが、Cだった。Cは自分の思い通りにいかなければ、見境なく暴力をふるうような凶暴な性格だった。裁判でADHDの傾向が高いと指摘されていたこともあり、きちんと性格を理解して受け止めてくれる友人もろくにいなかった。
Aは、そんなCの暴力的な性格に憧れのようなものを抱いていたようだ。AはCの真似をしてサバイバルナイフを振り回したり、エアガンで無差別な攻撃をしたりするようになった。さらにAは酒癖が非常に悪かった。酒を飲むと別人のように見境なく暴力行為に及ぶのだ。
こんなグループとたまたま先輩を介して知り合ったのが、犠牲者の上村遼太君だった。島根県の西ノ島で小学六年の夏まですごしていたが、両親の離婚後しばらくして四人のきょうだいとともに川崎に帰ってきた。だが、母親は二つの仕事を掛け持ちしていただけでなく、恋人の男性をマンションに入れて同棲をしていた。そんな環境ゆえか、遼太君は夜遅くまで家に帰らず、Aたちとつるむようになっていたのだ。
グループの少年たちは、ゲームセンターでガンダムのゲームをしたり、携帯でアニメやゲームを楽しんだりしてつながっていた。金がなければ、万引きや、賽銭泥棒をすることもあった。3学期が始まる頃には、遼太君は学校へまったく行かなくなっていた。学校側も何度も親に連絡を取った。33回にわたって親に連絡をし、五回も家庭訪問をしたのだ。だが、遼太君を直接説得する機会は得られずじまいだった。
事件が起こるのは、遼太君がAたちと知り合って1カ月半ほどした後のことだった。
ある日、遼太君の中学の不良の先輩Xが、Aが酔った拍子に遼太君を暴行したことを知り、それを口実に賽銭泥棒で取った金を脅し取ろうと考えた。そしてAの家に乗り込んで警察沙汰を起こすのだ。
AはXに狙われたのは遼太君が告げ口したせいだと逆恨みし、2月19日の深夜、酒を飲んだ勢いもあって、遼太君を呼び出す。そしてB、Cとともに多摩川の河川敷につれて行った。河川敷は真っ暗でひとけがなかった。Aは遼太君を殴るだけにするつもりだった。だが、Cが持っていたカッターを差し出し、Aは虚勢を張ってそれでもって遼太君を切りつけた。Aは血で服が汚れたのを見て思った。
こいつを帰したら俺が捕まる。Xにも殺される。
そして殺害を決意。
Aは遼太君を全裸にしてカッターで首を切りはじめたが、気が引けて致命傷を負わせられない。BやCにもカッターを渡してくり返し切らせても同じだった。仕方なく、川で泳がせて溺死させようともした。だが、遼太君は泳いで一向に沈んでくれない。一時間ほどが経った後、Aは腹をくくって、思い切り遼太君の首を切りつけた。ついに遼太君は動かなくなった。
遼太君はまだかろうじて息があり、A、B、Cはそれをわかっていた。だが、助けることなく河川敷を去った。翌朝、遼太君の無残な遺体は見つかったのである。
この事件を取材しながら私が感じたのは、「家族」とは何かということだった。
A、B、Cの行為が残虐であり、決して許されるものではないことは明らかだ。彼らを遼太君と同じ目に合わせろという声も理解できなくもない。ただ、日本の法律ではそれはできないし、感情的な意見をぶつけてもしかたない。ただ、それ以上に加害少年の声を直に聞いたり、被害者遺族にインタビューをしたり、友人たちの話を聞いたりしていると、グループの少年たちのほとんどが家族に居場所を見つけられなかった者だということがわかった。
同じグループにいた少年の一人はこう語っていた。
「うちはシングルマザーなんだ。俺はずっといじめられて不登校で高校にも行かなかった。俺がAたちと一緒にいたのは寂しかったからだね。別にAやBと友達だと思ってなかった。寂しさを紛らわせられればそれでよかった」
家庭で母親はどうしていたのかといえば、韓流スターにはまってDVDを見たり、コンサートに通い詰めたりして、彼とほとんど向き合っていなかったという。BやCもまた親に構ってもらえなかった上、Aのことを友人と思っていなかったと語っていた。単なるヒマつぶしや、寂しさを紛らわす相手でしかなかったのだ。
少年たちをそんな孤独に追いやったのは何だったのか。私は少なからず家族の影響が大きいと思う。加害者たちの親も、グループに集まっていた少年たちの親も、子供を愛していなかったわけではなかっただろう。だが、きちんと子供と向き合っていたと言えるだろうか。詳しいことは、拙著『43回の殺意 川崎中1男性生徒殺害事件の深層』を読んで、それぞれで考えていただきたい。
この事件は、当初残忍な不良たちが犯した凶悪事件のように報じられた。だが、私は少年たちが抱えていた家族の問題は、現代の大勢の少年たちに敷衍する問題だと思っている。私は加害少年たちを擁護したいのではなく、根本的な原因に目を向けなければならない必要性があると考えているだけだし、本書を著したのはそのためだ。親も、教育者も、世間も、その「問題」をしっかりと見つめることでしか、再発防止の実現は難しいだろう。この事件ルポがその一助となればと願っている。
********
2018年1月13日(土)に、本書発売に合わせ、「少年事件を報じるということ」と題して、本屋B&Bにてトークイベントを行います。著者の石井光太さんの他、佐世保小6同級生殺害事件を追った『謝るなら、いつでもおいで』(集英社)の著者で、毎日新聞記者の川名壮志さんをお招きし、語っていただきます。気になった方は本屋B&Bの公式サイトで詳細をご確認ください。
■本屋B&B
http://bookandbeer.com/