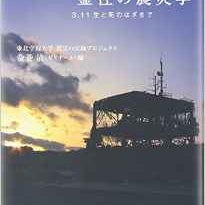車に戻った上野は、「俺はいったい何をやっているんだろう」と思いつつ、女性客に対する説教をやめることができなかった。
「いいですか、その上司は奥さんと別れるなんて言ってるようだけど、絶対に別れたりしませんよ。そんなもの、不倫を継続したい男の常套句です。そんな関係をいくら続けたって、最後に捨てられるのはあなたの方に決まってます」
「男はみんなそう言うっていうけれど、それって本当なんでしょうか」
「本当です。間違いない。そんなふしだらな関係、もう明日でやめにした方がいい」
「はあ」
上野の剣幕に、女性はきょとんとしてしまった。
「でも……」
「どうしてもやめられないというのなら、どうしてもやめられないなら……この場で僕とつき合うことにしなさい」
話が思いがけない方向に転がり始めた。
「えっ、いま何っておっしゃったんですか」
「僕でよければ、絶対にあなたの面倒を見てあげるから、だから……いまここで僕とつき合うと言いなさい。いや、僕とつき合え!」
最後は思わず、命令口調になってしまった。普通の女性だったらここで車を降りてしまうところだろうが、彼女は少し変わっていた。
「あの、一週間ほどお返事を待っていただけますか」
そして一週間後、上野が渡した名刺の電話番号に、彼女から本当に電話がかかってきた。
「私でよかったら、おつき合いしていただけますか」
上野は天にも昇る気持ちだった。瓢箪から駒とは、まさにこのことである。彼女はこの一週間で、上司との関係にきっぱりとケリをつけたに違いない。
彼女は、丸の内に本社を構える大手商社の系列企業に勤めるOLだった。父親はエネルギー関連企業の重役で、東京の西部の街に広大な屋敷を構えていた。母親が病気で早く亡くなっていたので、彼女はその広大な屋敷に父親とふたり切りで暮らしていた。年齢は30代の後半。上野より一回り以上も若い。いまどき珍しく奥ゆかしい雰囲気を持った、小柄な女性である。
上野が言う。
 山田清機
山田清機