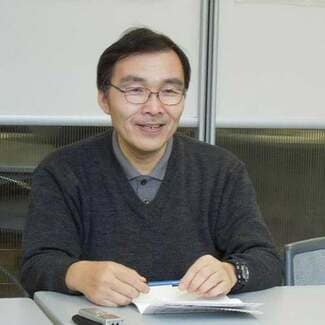その後、喜久井さんは『不登校新聞』や『シューレ大学』といった不登校やひきこもり、生きづらさを抱えた人とのつながりをえることで、自分を偽らずにすごせる場を得ます。人は居場所(本当の自分でいられる場・関係)を得ることで社会参加への道が切り開けます。喜久井さんもその理屈は同じだったようで、現在は、ひきこもり当事者のメディア『ひきポス』や『不登校新聞』で記事を書きつつ、図書館でもアルバイトをして暮らしています。
そんな喜久井さんが昨年、ちょっと晴れやかな顔で「サンタをやってきたよ」と話してくれました。
バイト先で声をかけられた仕事は、図書館内で催される「絵本のお話会」のあと、サンタに扮して子どもたちにプレゼントを渡すというもの。彼は寡黙でやせ形で、けっして陽気なタイプではありません。ビジュアル的には自他ともに不向きであるとわかっています。しかし、「その役を自分がやってもいいのか」と不思議なモチベーションが生まれ、仕事を快諾します。
募る期待と不安を胸にやってきたイベント当日。やせっぽちの喜久井サンタは、子どもたちから身を隠し、職員の呼びかけにより「メリークリスマース」と言いながら登場。すると子どもらは「サンタだ!!」叫びんで、元ひきこもりのもとに殺到。喜久井サンタは、子どもたちにもみくちゃにされ、うろたえ、付けヒゲゆえに息も絶え絶えにプレゼントを配布。子どもの野性味に圧倒されつつ退散すると、ふと「たまには親に連絡してみてもいいかも」と思ったそうです。
喜久井さんは、自分への罪悪感と同じぐらい強い気持ちで、親を恨んできました。子ども時代の自分を不幸にしたのは親のせいだ、と。しかし今、目の前の子どもたちに圧倒されてみると「親はよく世話をしていたなあ」と思ったんだそうです。
その後、喜久井さんは15年ぶりに両親と食卓を囲んでいます。ひさしぶりの食事は「複雑な気持ちだった」と語っており、けっしてよい思い出だけではなかったそうです。ただし、世間では30歳をすぎると「親の背中が見えてくる」と言いますが、ひきこもっていた彼も30歳を超えて親への思いが変わったようです。
喜久井さんが「殺されるかもしれない」「死ぬしかない」と追いつめられながらも、その思いが変わったのは居場所(本当の自分でいられる場や関係)と出番(サンタ)を得たからでした。練馬事件の報道を聞くたびに、私は心が痛みます。殺された長男も喜久井さんと同じような孤立感に苦しんでいたのではないか。もしも家族だけで苦しさを抱えず、社会の側に「ひきこもりの人の居場所と出番」がもっと整備されていたら思うからです。「殺す」以外の選択肢、これが社会のなかで今、議論しなければいけないことではないでしょうか。(文/石井志昂)
 石井志昂
石井志昂