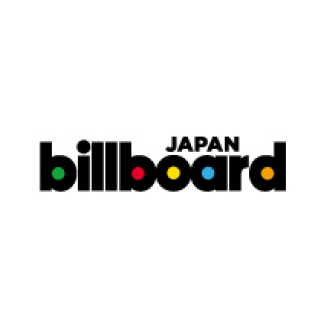ジョシュ・キスカ(ボーカル)、ジェイク・キスカ(ギター)、サム・キスカ(ベース)、ダニー・ワグナー(ドラム)の4人から成る米ミシガン州フランケンムース出身のロック・バンド=グレタ・ヴァン・フリート。日本での知名度は“ほどほど”といったところだが、2017年リリースのEP『フロム・ザ・ファイアーズ』が【第61回グラミー賞】で<最優秀ロック・アルバム>を受賞し、翌2018に発表した1stアルバム『アンセム・オブ・ザ・ピースフル・アーミー』が、米ビルボード・アルバム・チャート“Billboard 200”で3位、ロック・アルバム・チャートでは1位を記録するなどデビューからの功績は輝かしく、全米、欧州では高い知名度と評価を得ている。
本作は、その『アンセム・オブ・ザ・ピースフル・アーミー』から約2年半ぶり、2作目のスタジオ・アルバム。処女作の大成功によるプレッシャーや、新型コロナウイルス感染による世界情勢の悪化など、様々な懸念点がありながらも完成させただけはある意欲作で、キャリアと年齢を重ねたからこその味わいや深みが、前作からの成長過程として伺える。もちろん社会情勢を反映した哲学的な歌詞と、クラシック・ロックを再現したサウンドの輝きは健在。
米メインストリーム・ロック・ソング・チャートで1位を獲得した1stシングルの「マイ・ウェイ、スーン」では、目に耳にしてきたことをどこか冷めた目で達観し「目論見は投げ捨てて、何も負わずに生きていく」と我が道標を高らかに歌い上げている。ジョシュのハイトーン、緊張感漲るジェイクのギター・プレイもすばらしく、サウンドに直結したVHS世代を彷彿させるレトロなミュージック・ビデオも洒落た仕上がりだった。
前作のオープニング「エイジ・オブ・マン」の続編的な意味合いをもつ7分弱の大作「エイジ・オブ・マシーン」にも同じように「自由」や「解放」といった表現が使われている。サウンドはもちろん、宗教的な言い回しを含んだ歌詞の世界観もかつてのレジェンドに影響を受けた印象。3曲目のシングル「ヒート・アバヴ」は、「地球の嘆きよ」からはじまる破壊的なニュアンスの中にも「この世界には見えない愛がたくさん残っている」というポジティヴな意味合いが込められた、メッセージ・ソング。前者がツェッペリンなら、後者はREOスピードワゴンといったところか。MVではクイーンの面影もみせるなど、彼等のルーツといえる(であろう)要素が滲み出た。
鬱々と重たい中にも「いつか時は満ちる 沈黙を破り 俺たちは歌う」と向上を伺わせた「ブロークン・ベルズ」は、ジョシュの儚げなボーカルとベース・ラインが切ないロッカ・バラード。昨今の社会情勢による精神への影響については、曲を通じて考えさせられるものがあった。シンプルだからこそダイレクトに伝わる、ピアノとアコースティック・ギターの音色が切なく響く「ティアーズ・オブ・レイン」~3連ミディアムの「スターダスト・コーズ」しかり。しかし、どちらの曲においてもジョシュ・キスカの突き抜ける高音には驚かされる。
高音といえば、ロバート・プラントの再来というべく「ビルト・バイ・ネイションズ」もギターの絡み具合などがツェッペリン直結。英国産ではハンブル・パイを彷彿させるプレイの「キャラヴェル」~自由であることを強調した「トリップ・ザ・ライト・ファンタスティック」、一方でラッシュのようなギター・トリップを聴かせる「ザ・バーバリアンズ」なんかもあり、彼等の親以上の世代が懐かしさに浸れる、そんなクラシック・ロックが今作も満載。プロデューサーのグレッグ・カースティンによる手腕も十二分に発揮された。
このように、グレタ・ヴァン・フリートのサウンドは“何かっぽい”と比喩されがちで、【グラミー賞】を受賞した際にもメディアや評論家からはいくつかの批判が投げかけられた。ミュージシャンにおいて、ネガティヴな声は悪い意味だけでなく「それだけ興味をもたれている」という捉え方もできるワケだが、メンバーにとっては煮え切らない思いも当然あるだろう。沸々とした想いが歌詞にもいくつか反映しているように受け取れる。もちろん、筆者は“~っぽい”を否定的な意味合いで表現したわけではないが、捉え方はそれぞれ、難しいところではある……。
本作について、それぞれが寄せたメッセージには「これまでとは変わった」という考え方や価値観の変化が共通している。また、人間らしい暮らし、愛、平和、平等などパンデミックを受けての想い、願いも感じられた。ハードなサウンド&ボーカルの中にも繊細なメッセージが込められた『ザ・バトル・アット・ガーデンズ・ゲート』。12曲に掲げられたシンボル・マークも、決して“形だけ”のものではない。
Text: 本家 一成