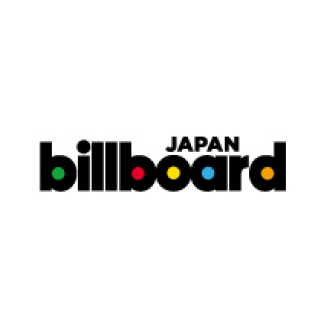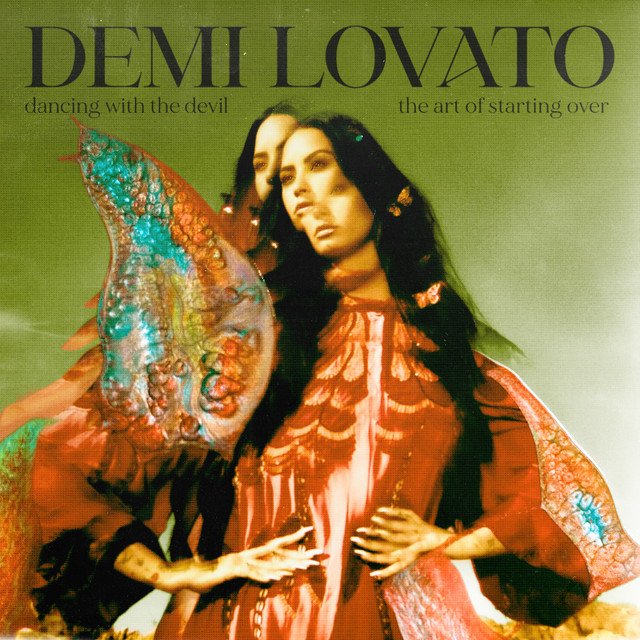
2021年3月23日に公開されたYouTubeのドキュメンタリー番組『Demi Lovato: Dancing with the Devil』では、薬物の過剰摂取で危機的状況に陥ったことや性的暴行を受けた経験など、思い返すのも苦しい出来事と精神状態をオープンにしたデミ・ロヴァート。問題がすべて解決したわけではないだろうが、前進しようという意思が伺えたのは何よりだった。
3年前のオーバードーズによる惨事を赤裸々に綴ったタイトル曲「dancing with the devil」はじめ、本作にはドキュメンタリーに直結した“あれから今に至るまで”のエピソードが詰まっている。「ソーリー・ノット・ソーリー」などのヒットを生んだ前作『テル・ミー・ユー・ラブ・ミー』(2017年)に続く7枚目のスタジオ・アルバムではあるが、コンセプトからすると過去6作とは別枠にあるイメージ。
その「dancing with the devil」は、ロックバンドSR-71のリード・ヴォーカル=ミッチ・アランによるプロデュース曲で、映画のエンドロールで流れてきそうな曲の迫力と、それに負けないデミの凄まじい声圧に圧倒される。中毒症状やトラウマを生々しく描いたミュージック・ビデオの終盤に、首に刻まれた「Survivor」の文字(タトゥー)がフィーチャーされるシーンがあるが、これも(生き残ろうという)前向きな姿勢を意味しているように思える。
もう一つのタイトル曲「the art of starting over」は、題が示す通り「闇から抜け出してやり直してみせる」という強い決意を乗せた意欲作。アルバム・タイトルを「dancing with the devil」で終わらせず、この曲に繋げたのも納得できる。曲調はオルタナっぽく若干地味ではあるが、相応の味わい深さがいい。
アルバムの1曲目に抜擢された「anyone」は、昨年1月に開催された【第62回グラミー賞】で約2年ぶりにステージ復帰した際披露し、エモーショナルなパフォーマンスが高い評価を得た。誰かに救いを求めようともがく様を、絶唱というべく歌で表現するあたりは流石の業。バラードだが、素晴らしいボーカル・ワークによりオープニングを飾るに相応しい存在感を放っている。制作には、リアーナの作品で知られるビビ・ブレリーが参加した。
3曲目の「icu (madison’s lullaby)」は、旋律もボーカルも優しいタッチのメロウ・チューン。タイトルにもある妹のマディソンにあてた曲で、病院に搬送された際についていてくれた彼女を、妹だと認識できなかったという恐ろしい体験が書かれている。なお、このICUには「集中治療室」と「I See You」の2つの意味が含まれているのだそう。この曲から、孤独についてシビアな解釈を示したバロック・ポップ風の「lonely people」、見ていて欲しい誰かへ向けたアコースティック・メロウ「the way you don't look at me」と、穏やかな流れが続く。摂食障害について歌った次曲「melon cake」も、軽快なポップ・サウンドで歌詞の重さを緩和した。
ゲストは4人。友人でもあるアリアナ・グランデとの初コラボレーション「met him last night」は、彼女の作品でもお馴染みのトミー・ブラウンが手掛けた曲で、アリアナ寄りのR&Bっぽいトラックが“らしい”仕上がり。お互いパワーのあるハイトーンを得意としているが、被らないよう配慮し合ったハーモニーで調和した。フィーメール・ラッパーのスウィーティーをゲストに、プロダクション・チーム=ポップ&オークをプロデューサーに迎えた「my girlfriends are my boyfriend」も、R&Bやヒップホップをベースとした曲。女友達のアレコレをテーマにした歌詞と、スウィーティーのラップがよく溶け込んでいる。
交際報道が浮上するほど仲が深まった(という)ノア・サイラスとのコラボ曲「easy」は、マシュー・コーマが手掛けたマイナー調のバラードで、もののあはれや切なさを両者とも情感込めて歌い上げた。圧力や評価云々について歌ったパワー・バラード「what other people say」は、唯一男性として参加したオーストラリアのシンガー・ソングライター=サム・フィッシャーとのデュエットで、ピンクとネイト・ルイスの「ジャスト・ギブ・ミー・ア・リーズン」に匹敵する相性の良さには込み上げるものがある。
ソングライターとして参加したローレン・アキリーナの色味が感じられるフェミニンなミディアム「carefully」や、風通しの良いライトなポップ・ソング「the kind of lover i am」など恋愛絡みの曲もあり、元婚約者のマックス・エーリックに向けたとされる「15 minutes」では未練があるのか皮肉っているのか、意味深なメッセージを高らかに歌っている。複雑な関係にあった亡き父へのメッセージ・ソング「butterfly」、同じ苦しみを抱えている人たちと共感し、ハッピーエンドを見出そうという思いを込めた最終曲「good place」など、いずれもデミ・ロヴァートのリアルな感情が垣間見えた。
全19曲、若干詰め込み過ぎた感はあるが、3年という長い期間にあった出来事を集約するとむしろ少ないのかもしれない。そんな理由からか、昨今のブームに則ってかは定かでないが、発売直後には早速デラックス・エディションもリリースされている。内容がヘヴィなだけに大衆受けしないかもしれないが、これまでで最も彼女らしいアルバム、といえるかもしれない。
Text: 本家 一成