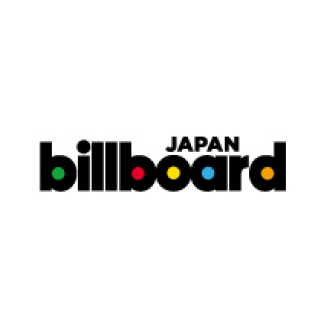今年は、米ビルボード・ソング・チャート“Hot 100”で首位獲得を果たした、ショーン・メンデス&カミラ・カベロの「Senorita」や、同チャートでTOP10入りしたベニー・ブランコの「Eastside」など、自身がプロデュースしたタイトルを次々とヒットさせている、ノルウェー出身のDJ/プロデューサー=カシミア・キャット。その合間を縫って制作されたのが、本作『プリンセス・キャットガール』で、アルバムのリリースまでには2曲のシングルも発表している。
そのうちの1曲「Emotions」は、スウェーデン出身の女性エレポップ・シンガー、 トーヴ・スティルケとの共作曲。前月に公開されたミュージック・ビデオには、架空のキャラクターでアルバムのタイトルでもある『Princess Catgirl』が、森の中でパフォーマンスするシーンが起用されている。Princess Catgirlについては、シャイで人前に出るのが苦手だった自身の代わりとして、また、自分を安心させてくれる存在だとも話している。アルバムのアートワークにデザインされたのも、同キャラクター。
もう1曲の先行トラックは、アルバムのオープニングを飾る「For Your Eyes Only」。クレジットはされていないが、米NYを拠点とする音楽プロジェクト=フランシス・アンド・ザ・ライツがキーボードとバック・コーラスを担当している。タイトルをひたすら繰り返すフックと、スペイシーなサウンドが中毒性抜群で、壮大さを演出するエンディングが特にいい。フランシス・アンド・ザ・ライツとはデビュー・アルバム『9』(2017年)収録の「Wild Love」でも共演し、今作でも相性の良さをアピールした。ソングライター/プロデューサーには、前述のベニー・ブランコもクレジットされている。
2曲目の「Watergirl」は、同名タイトルであるクリスティーナ・アギレラの全米No.1ソング「What a Girl Wants」(1999年)がサンプリングされた、キュートなエレクトロ・ポップ。歌詞の一部には、オーストラリアの女性シンガーソングライター=コタ・バンクスというアーティストの楽曲も含まれている。原曲のイメージが強いからか、「Emotions」以上のインパクトをもつ本作の目玉ともいえる一曲で、曲後半にはアルバム中唯一エフェクト加工されていないボーカルも登場する。
間髪入れずはじまる「Back for You」は、ベニー・ブランコと音楽プロデューサー/ソングライターのソフィーが制作を担当。ソフィーは、前作『9』でも数曲に参加している。原型は留めていないが、ボーカルは「Luv」(2016年)のヒットで知られるカナダ出身のシンガー/ラッパーのトリー・レーンズによるもの。その「Luv」のプロデュースはカシミア・キャットとベニー・ブランコが務め、翌2017年の【第59回グラミー賞】で<最優秀R&Bソング>にノミネートされた。
5曲目の「Moo」には、昨年6月に死去したラッパーのエクスエクスエクステンタシオンが残した「Moonlight」(2018年)という曲がサンプル使用されている。1分33秒とインタールードのような短さではあるが、無造作に重ね合わせたエレクトロ・サウンドと、下に敷かれた原曲のトラックが、いつまでも耳に残り離れない。カシミア・キャットは、「Moonlight」の制作者であるジョン・カニンガムに使用の許可を得たことを感謝し、ツイッターではフェスの様子を撮影したショート・ビデオも公開している。
続く「Without You」は、日本でも高い人気を誇るヘイリー・スタインフェルドの「Love Myself」(2015年)を使用したエレクトロニック・ソング。「For Your Eyes Only」同様、この曲もボーカル・パートより繊細な音作りのインストゥルメンタルこそが聴きどころ。そこからはじまる、メランコリックなメロディラインの「Princess Catgirl」でアルバムは終了。全7曲、トータル20分弱とほぼEP盤に近いコンパクトな出来だが、本人は表現したい音楽と成長を示すには、何ら問題ないとしている。たしかに、前作『9』も全10曲と小粒ながら、強いインパクトを残した傑作だった。
ここ最近、ヒップホップ系アーティストの間でも主流となった、ゲスト・クレジットに依存しないスタイルで勝負したカシミア・キャット。 ボーカルがメインだった前作『9』とは対照に、自身の生み出すサウンドを主とした、フォームへの回帰を表した作品ともいえる。「Senorita」や「Eastside」はあくまでプロデュース作品で、個人プロジェクトはきちんと一線を画いているところも、アーティストとしてのプライドみたいなものを感じる。
Text: 本家 一成