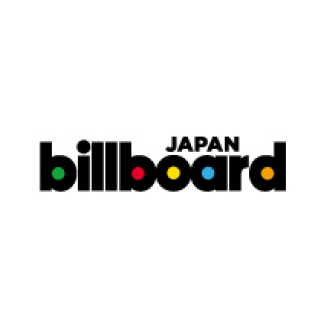近年、白人のフィーメール・ラッパーとしては最も大きな成功を収めたといえる、イギー・アゼリア。米ビルボード・ソング・チャート“Hot 100”で通算7週のNo.1をマークした「ファンシーfeat.チャーリーXCX」(2014年)収録のデビュー・アルバム『ザ・ニュー・クラシック』(2014年 / 全米3位)に続く、2作目のスタジオ・アルバム『イン・マイ・ディフェンス』が遂に完成した。
その「ファンシー」の大ヒットから早5年が経過した2019年現在、カーディ・Bやリゾといった女性ラッパーたちがチャートを荒らし、再び活気を取り戻しつつある……が、イギーの扱いは“ゴシップ・ネタ”ばかりで、同2014年に最高3位をマークした「ブラック・ウィドウfeat.リタ・オラ」以降、ヒットからは遠ざかっている。
たとえば、胸や顔の整形疑惑、ラッパーのタイガと浮上した熱愛報道、日本でも大きく取り上げられた、ヌード画像の流出など。それはそれで、フィーメール・ラッパーらしくはあるが、それも「アーティストとしての功績」あってこそ。そういった意味では、ちょっと残念な状態が続いている……と、いえなくもない。エミネムには「イギーのアバズレと一緒にすんな」とかディスられてるし……。
とはいえ、ヒット=すばらしい作品というのもまた、違うハナシで、昨年夏にリリースしたEP盤『サバイブ・ザ・サマー』は、小粒ながらも底意地をみせつけた傑作だった。彼女のいいところは、何とか売ってやろうと「ファンシー」のようなポップ路線に回帰しないところだ。ここ5年の作品を振り返ると、年々エグさが増している。
エグさにも色々種類があるが、イギーの場合は“セックス・シンボル”的要素が強まった、これに尽きる。全12曲、和訳したら日本ではとても流せないような曲ばかり。お世辞にも「意味あるエロさ」と言えないレベルで、何ていうかもう、ヤケクソになっているようにも思えるが……彼女独自の「立ち位置」を確立したようにもとれなくない。
アルバムのリリース直前に公開した「Just Wanna」が特にヒドい。冒頭から「顔にアソコを押し付ける」と繰り返し、フックではひたすら“したい”ことを訴える。ハードなトラックに乗せて生々しい性交の段取りを綴る「Pussy Pop」も、キーステーションではとても流せないレベルの内容だ。囁き系のラップ・フローがさらに卑猥さをかきたてる。
参加ゲストは3人。こちらもここ最近はヒットから遠ざかっている、米アトランタ出身の若手ラッパー=リル・ヨッティをフィーチャーした「Hoemita」、モデルとしても活躍する、米ミシガン州出身の女性シンガー、カッシュ・ドールとタッグを組んだ「Fuck It Up」、他アーティストの作品に多数起用されている、ジューシー・Jとの「Freak of the Week」。いずれもフロアライクなトラックで、リリックも<Parental Advisory>必須の自由過ぎる表現がウリ。
セックスネタとは、ちょっと違うニュアンスの曲もある。「売れなくなったヤツ」とディスる誰かを「使い古した女」と罵り、見事なヒップを武器に誰にも真似できないアレをすると口語する、先行シングルの「Sally Walker」。この曲では、「周りと同じ事はしない」と強気の姿勢をみせ、自身が“まだ終わってない”ことを断言した。交通事故死した女性の裁判~葬儀の様子を皮肉るミュージック・ビデオも、(不謹慎だが)彼女らしいといえばらしい仕上がり。冒頭の「Freak of the Week」でも、自身が落ち目であることをネタにしている。
5月にリリースした2ndシングル「Started」では、名声と金について歌っている。これも、ある意味「ディスられた誰か」に対するあてつけだろう。フィーメール・ラッパーのリリックにありがちな“私はこれだけ成功したんだ”的な内容。車いすの年配男性と(偽装?)結婚式を挙げ、セレブ生活を満喫するという、一部の女性には耳の痛いネタを放り込んだミュージック・ビデオは傑作。その他、人種差別について堂々皮肉る「Clap Back」や、ディオールの衣装が歌詞に登場する「Comme des Garcons」などもある。
サウンドは、トラップを基としたヒップホップを主としている。メロウ系や流行りのレゲエ、ラテン系、オルタナR&Bっぽい歌モノも一切ない。プロデューサー陣が少ないせいか、はっきり言って「ずっと同じような曲を聴いている」感否めないが、超人気アーティストをゲストに迎えたカーディ・Bのデビュー作や、ポップとヒップホップの狭間をいくアリアナ・グランデの『thank u, next』ような路線に転身しなかっただけでも、芯を貫いたといえるのではないだろうか。
Text: 本家 一成