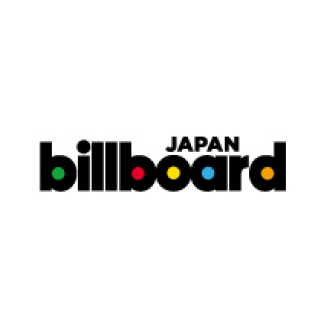チェンバロ奏者スキップ・センペが5月3日から3日間開催されたクラシック音楽祭【ラ・フォル・ジュルネTOKYO】に2公演登場、初日の公演レポートが到着した。
「フランスの鍵盤音楽は、それ自体が私にとっての“旅”です。違う世界へ、何百年もの時を越えて――弾いているだけで旅をしている気分です。」
フランス発のクラシック音楽フェス【ラ・フォル・ジュルネTOKYO】2019年のテーマは『ボヤージュ 旅から生まれた音楽(ものがたり)』。毎年無数の演奏者が演奏会を開くなか、それぞれがテーマにどう答えるか?が面白い。しかしチェンバロ奏者スキップ・センペの演奏した音楽は一見、むしろ旅とは無縁そうだった。演目の大半は17世紀フランスの作曲家たち、ルイ・クープランやシャンボニエール、ダングルベールらの曲……ほぼ故郷とパリでしか活動しなかった作曲家たちだ。唯一、ヨーロッパ中を旅したドイツ出身の作曲家フローベルガーの曲も含まれてはいたけれど、その1曲で“旅”を語りつくすにはどうにも薄い。それで直接聞いてみたところ、上のような答えが返ってきたというわけだ。
とはいえ、音楽にふれるということはそれ自体に“旅”の要素がたっぷり沁み込んでいるのかもしれない。そんな話をレポートしてみようと思う。
今回の【ラ・フォル・ジュルネTOKYO】でセンペが登場した2回のソロリサイタルは、どちらも時間が極端だった。夜遅く始まり22:30で終わる初日最後の回と、朝9:30に始まる二日目最初の回。1日がまだほとんど始まっていない時間か、もう後は帰るだけの時間。聴き手の多くは比較的高い集中力で音楽に向き合えたのではないだろうか。そういう空気が会場にあった。
そのうえ演奏会場はどちらも、東京国際フォーラム屈指の“秘密の部屋”めいた空気があるD7ホール。天井の高い黒壁の空間で、見立てによっては朝でも夜空の下に閉じ込められた(あるいは、好んで閉じこもりにきた)気分になる。チェンバロ独奏という秘めやかな音楽とじっくり対話するにはうってつけの環境だ。
18世紀にピアノが開発され普及してゆく前まで、王侯や貴紳たちの私的空間に置かれていた家具のような鍵盤楽器。それがチェンバロだ。ピアノのように無数の金属弦を張ってあるが、鍵盤と連動した爪で弦をはじいて音を出す機構上、どのように鍵盤を叩いても一音ごとの音量そのものは変わらない。それで後年は弦を1音ごと複数本ずつ張り、鍵盤を2段にして爪ではじかれる弦の数を変え、大きめの音量と小さめの音量を使い分けられるようにしたものも現れた(当該会場でセンペに用意されていたのもその種の二段鍵盤チェンバロ)。
しかしセンペは今回、ほとんどの演奏を下鍵盤で弾いた。古い一段鍵盤の楽器を想定した音楽を弾いているという意思表示だろうか。当時の作曲家たちは上述のような特性を熟知したうえで、音量が欲しい場面では音の数を増やして響きを増すなど、チェンバロ音楽ならではの工夫を徹底して楽譜に盛り込んでいるので、鍵盤を弾き分けて音量効果をねらわずとも起伏に富んだ音楽はできる。もちろん、チェンバロ演奏の技法を熟知した弾き手なら、ということだが。
その点センペが全く心配のない弾き手なのはいうまでもない。数多くの門弟を育ててきた歴年の名手だ。鍵盤にふれるたび、会場の響きの具合を確かめるように丁寧に鳴らしながら弾き進めてゆく。明瞭な音の重ね方、楽器の個体差と空間の音響条件にあわせた音作り。17世紀フランスのチェンバロ音楽は、演奏するさい即興的にたくさんの音を盛り込んでゆく必要がある。結果的に、演奏のたびごと一期一会の音楽ができあがる。そうやって彼が弾き進めてゆくにつれ、客席はますます音楽に引き寄せられてゆく。
その聴き手は演目を事前にいっさい聞かされていない。2公演とも【ラ・フォル・ジュルネTOKYO】の名物企画“カルト・ブランシュ”、演目非告知公演だったのだ。それも、終演後に会場出てすぐのボードで告知するという手の込みよう。作曲者いかんで音楽を判断するのはやめて、純粋に音の流れに身をまかせた人もいただろう。あるいは(筆者のように)作曲家や演目の時代背景を想像しながら、いつ誰がどこで書いた音楽だったか探りながら聴いた人もいただろう。いずれにせよ、その演目は数百年前の、日本ではないどこかで書かれたものであるに違いない。そう考えて耳を澄ませている時点で、客席側でもそれぞれが心の時間旅行をしていたに等しい。音楽を聴くことは、常にそういう“旅”の感覚と不可分なのかもしれない。
初日夜の公演は、筆者の感じではセンペの期待より一瞬早く拍手が出る印象だった。とても興奮を誘う、静々と刺激的な演奏だったから。穏当で学究的な印象もあるチェンバロ音楽の世界に、独特の躍動感ある刺激を持ち込んだのがかつてのセンペの録音群だったが、会場の響きに合わせたのか、録音よりも落ち着いて静かな風格のある演奏だったように筆者は感じた。
とはいえ当人曰く「録音と実演は等価物にしたい」。演目本来の即興性を越えて、センペは録音物にも大きな期待を持っている。自身Paradizoというレーベルを立ち上げ、定期的にリリースを絶やさずに来たのもその考えからだ。「録音物は編集を通じて洗練にたどりつけます。生演奏はそうはいかないので、そのぶん練習を重ねて望まなくてはなりません。いずれにせよ、録音物がなければ出会えなかった過去の素晴しい演奏家はたくさんいます。これからもそうでしょう。いまチェンバロを学ぶ人たちは、グスタフ・レオンハルト(※センペの師で2012年に亡くなった、チェンバロ音楽復興の立役者たるチェンバロ奏者)の実演には触れられないのですから。」数十年来の“パリ暮らしのアメリカ人”になる前、彼がジャズの聖地ニューオリンズで生まれ育った人だったことも思い起こされる。
2日目朝の公演では、前夜には一切聴かれなかった18世紀フランスの大家、フランソワ・クープラン(ルイ・クープランの甥)の音楽が最後に演奏された。当時の工芸品に描かれた理想郷の羊飼いたちを彷彿とさせる、泰然自若の指まわりで紡ぎ出される牧歌曲ミュゼットでは、のどかなバグパイプの音を思わせる固執音型のなめらかさも、立ち現れる音楽の柔和な響きも印象的だった。師レオンハルトに近いたたずまいさえ感じさせる穏やかな風格は、弾く楽器ごとの個体差と真剣に向き合っていればこその結果かもしれない。
「チェンバロも時代や地域ごとにさまざま。社交的・外面的な魅力のあるものもあれば、内省的な魅力をもったものもあります。前者であればスカルラッティその他のスペインの演目もよかったでしょうが、今回の楽器はもっと玄妙で親密、フランスの音楽をすぐに思い浮かべました。実際にはドイツ18世紀のモデルですが、そうした楽器には(当時のドイツ人チェンバロ音楽家たちも手本にしていた)フランスの古い音楽がとくによく似合うのですよ。」
センペはこれら2公演でわずか数回、弾く鍵盤を上鍵盤に変えて聴き手をはっとさせる弱音を響かせた――死者への追悼曲(トンボー)でそのような弾き方をしたのが実に印象的だった。録音物を重んじてくれているおかげでCDを通じて日本でも愛されてきたセンペの貴重な実演、早くも次の機会が待ち遠しい。彼の旅の末に、私たち日本の聴き手の旅が待っている。TEXT:白沢達生
◎公演情報
【スキップ・センペのカルト・ブランシュ】
5月3日 (金・祝) 22:00 ~ 22:45
会場 東京国際フォーラム ホールD7:マゼラン