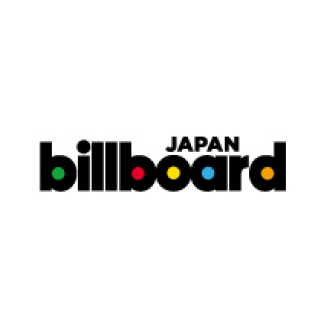1960年ドイツ生まれの名ピアニスト、アレクサンダー・ロンクヴィヒ(ロンクヴィッヒ、あるいはロンクィヒ、ロンクィッヒ、とも)は、長らく室内楽奏者としての演奏を耳にする機会ばかりだった。共演者名簿には、ヴァイオリンのフランク・ペーター・ツィンマーマン、シュロモ・ミンツ、チェロのハインリヒ・シフにスティーヴン・イッサーリスなど斯界の大物が顔を揃えており、名録音の数も多い。
ペースは遅いがECMなどから高水準のソロ録音も出すようになったのは、この十数年ほどのこと。以降ようやくソリストとしても来日するようになったロンクヴィヒが、新たに Alpha レーベルから音盤を出す、という報せ自体がうれしい驚きをもたらしてくれた。そして音に耳を傾け、さすが欧州各地から抜群の才能を探し当ててくる、いま世界で最も明敏な審美眼を誇るレーベルのひとつが白羽の矢を立てただけはある、と唸らされた。
収録されているのは、1828年11月19日にこの世を辞したシューベルトが、その直前に一気に書き上げたピアノソナタ第19番D.958、第20番D.959、第21番D.960という三部作、そしてこれも同年に書かれた3つの小品、D.946である。
シューベルト最晩年の作品は、繰り言のように、あるいは強迫観念的に似たパッセージを積み重ねていくかと思えば、突如あらぬ方へと転調したり、あるいはD.958の第4楽章のように、ふと立ち止まったと思ったら全く別のことを語り出してみたりもする。そのために、ともすれば単調か、あるいは散漫な印象を与えかねないのだが、ロンクヴィヒは、やや音を重ね気味にしたウェットなテヌート、音の粒を揃えたノンレガート、音の立ち上がりはよいが角のないセミ・スタッカート、ここぞというときの力感あるマルカートの4つを軸に、質感の異なる様々なタッチを緻密に使い分けて組み合わせ、丁寧な彫琢を施してゆくので、聴き手を飽きさせるようなことは微塵もない。
くぐもった声で呟くようなフィギュレーションも多い晩期シューベルトのピアノ作品は、減衰の遅いモダンピアノではペダリング技術の巧拙がモロに出る作品だが、ロンクヴィヒは響きが飽和することを避けてスッキリとした音世界を構築してゆく点も印象深い。
彼の音楽作りが最も前面に出ているのは第20番で、その造形の特徴は、敢えて作り出す微かな「不均衡」にある。第1楽章では、長短、短長のリズムグループの長いほうの音価を常に僅かに引き延ばすことを全曲を通じて徹底するし、2つ、ないしは3つの同じ音が続けて鳴る箇所でも、音価は常に不揃いにしている。第2楽章アンダンティーノの主題も第3楽章スケルツォ主題も跛行しているし、第4楽章はここまでの3つの楽章に較べればストレートだが、やはり言葉を繋ぐ箇所で、ひとつ呼吸を入れる。第21番D.960の第2楽章も、主題部はもちろん、流れるような中間部や、第3楽章スケルツォの暗鬱なトリオ部も、リズムは敢えて不揃いにされ、音楽に引っかかりを作ってゆく。
作為は決してこれみよがしなものではなく、ベースのテンポも保たれているために、違和感を感じるようなことはないのだが、ともすれば耳馴染みよくサラサラと流れていこうとしてしまいそうなパッセージをせきとめ、秘やかなつぶやきのつながりと堆積へと変えてゆく、それがロンクヴィヒの描くシューベルト最期の年の音楽だ。Text:川田朔也
◎リリース情報
『シューベルト:最期の年のピアノ作品』』
ALPHA433