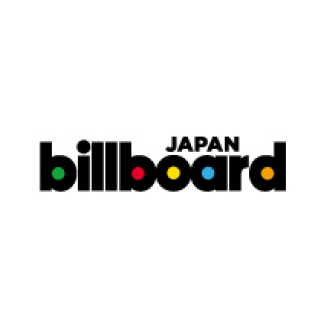いま「ピアノ」という言葉を使うときには、大抵はアクションはじめとする構造面の画期的な発明や、産業革命が可能にした工業技術を次々反映させ、音量を増してゆくとともに音域も広げて88鍵を備えるに至ったモダンピアノのことを指す。しかしクリストフォリの発明以来300余年、ピアノという楽器の辿った道は平坦でも一本道でもない。客席数2000を越えるホールでも映える豪壮なフルコンサートグランドの歴史は、長くはない。
それ以前の楽器は音楽史的な知見を深める道具に過ぎないのだろうか?
いや、たとえばこのディスクで弾かれている1848年のプレイエルは、サイズ的に室内楽的、という次元をもこえて、聴き慣れたモダンピアノとはかなり異なる独特な音色、平行弦ピアノならではの独特の響きをもっている。そんななか、ピリオド楽器による演奏と録音を精力的に行っている小倉貴久子が、ただでさえ録音のさほど多くないビゼーを弾いてくれるとは、うれしい不意打ちというもの。これがこのディスクの最初の大きなウリだ。
ビゼー(1838ー1875)は当然フランスの作曲家だが、冒頭に置かれた、メリのスタンザに着想を得た『ラインの歌』は、明らかにメンデルスゾーンやシューマンの系譜に連なる。比較的入手しやすいルイサダや福間洸太朗の録音もあるが、プレイエルから様々な音色を引き出す小倉のタッチが繰り延べる世界に改めて耳を奪われる。右手ユニゾンが旋律を担当する第2曲「出発」の後半にある喜悦に満ちた息の長いクレッシェンドや、ソプラノ声部とテノール声部の呼応に心ときめく終曲「帰郷」などでは、ダイナミック・レンジを十分に使い切って劇的な喚起力がある。第3曲「夢想」の和音に付き従われた優美な旋律や、第5曲「ないしょ話」での和声の推移につけられた折り目も丁寧だ。
こうした造形の緻密さと、繊細だが時に大胆で強靭な打鍵との共存が演奏の大きな特徴だ、リスト風の演奏会用序曲といった趣きで、遠く近くこだまの聞こえる『幻想的な狩り』、カチッとした7つの変奏から成る『半音階的幻想曲』のような高度な技巧を要する曲では、過敏なほどによく反応するプレイエルのブリリアントな響きも存分に愉しめる。フィールドやショパンの影響を色濃く残した1854年のノクターンと、意想外の和声進行をみせて後代のフォーレを予告するような1868年のノクターンの対比も面白い。
後半は『アルルの女』の作曲者自身によるピアノ独奏版で、オケ版とは一味もふた味も違うものの、管弦楽的でヴィヴィッドな色合いもまばゆく、実に鮮烈。ヴィンテージ・ワインのような馥郁たる薫りを醸し出だすプレイエルで開いてくれるビゼーの世界を、是非お確かめ頂きたい。Text:川田朔也