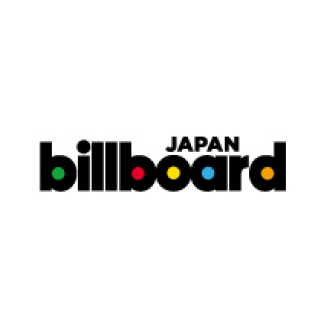1966年生まれ、ドイツの誇る名ヴァイオリニスト、テツラフによるバッハ無伴奏ソナタとパルティータ全曲録音は、本録音で3度目だ。最初が1993年のVirgin(現エラート)、次が2005年(ヘンスラー)。そして2015年に東京の紀尾井ホールで全曲演奏会でも披露したあと、このオンディーヌ録音ということになり、ちょうど干支が一巡りするごとに録音を重ねていることになる。
同じ曲集を同じ指揮者・団体などが繰り返して録音することは、大編制のジャンルでは珍しくない。ピアノを伴うヴァイオリン曲なら、相方のピアノ奏者が異なればいくつも録音があるのは不思議でもない。しかしバッハの無伴奏曲で3度の録音を、しかもいまだ老齢に達していない50そこそこの奏者が成し遂げるのは、それだけで事件である。
ロマンティックな趣きが強かった旧録音に較べて、この録音は引き締まった精悍な佇まいだ。たとえば第1パルティータ第7曲などが典型的で、思わせぶりなタメを最小限に抑制する。重い重音を鳴らすためには当然タイムラグとしてのタメは必須なのだが、第2ソナタ第4曲や、アルペッジョが連続する難曲シャコンヌ、第3パルティータ第4曲といった速いテンポでも所作はあくまでもスマートでありながら、正確かつしなやかなのだ。
この特徴は、全曲を通じて一貫している。重音の全てを無理に均等に鳴らしてひとつひとつを明瞭に聴かせることよりもなお、音楽のフローそのものに着眼点を置くことで、自然な息吹を生み出すのである。もちろん第3ソナタの第2曲フーガでは主旋律に対旋律などを優しく響かせるのだが、ここに思わせぶりな身振りはない。どこを切っても清明でいま生まれる音楽の息吹を慈しみ、あるがままに溢れ出るままにさせているかのようだ。
第1ソナタ第4曲プレストのVirgin盤は胸のすくような伸びやかさを感じたとして印象深いが、本録音では縦線を合わせるためのタメがある程度で、とにかく流麗の一語につきる。第1パルティータ第5曲サラバンドからドゥーブル、テンポ・ディ・ブーレ、ドゥーブル、という連なりも、Virgin盤では濃厚にロマンの漂う薫り高い演奏だった一方、新録音ではもっと均整の取れた清冽な音楽に仕上がっている。
スタッカートの連続で技巧的にも難易度の高い、かの有名な第2パルティータのシャコンヌでは、呆気ないほどアッサリと弾くのだが、その簡潔なスタイルでもってしても、この長大な金字塔的楽曲の威容が立ち現れてくるのは、テツラフが作品に可能なかぎり無理をさせずに陰翳を彫琢した結果だと言える。
第2ソナタ第2曲のアレグロ、第3ソナタ第3曲のフーガなどは、すべての声部が明瞭に聞こえるのみならず、それが一つの音楽に収斂してゆくダイナミズムを隠し持っている。この旧録音からの変化はしかし、秘やかかつ弾力あるしなやかな変化で、大きな声を出して、ここが変わった、あそこが変わった、と触れ回るような類いのものではない。あくまで抑制の効いたスタイリッシュな音楽は、的確なフレージングと、徹底して安定したボウイングによって実現されている。
ノルウェーの教会で収録されたという録音は、音響空間を感じさせるクリアだが暖色のトーンを生み出しており、クオリティも極めて高い。教会での録音は残響がたなびきすぎる録音も多いのだが、テツラフのバッハは、そうしたヴェールに包んで荘厳な雰囲気を醸し出すわけではない。そして、ペーター・グライナーのヴァイオリンも、ほどよくこなれて来たと思える。このアルバムも、テツラフによるバッハという円環を経巡る、新たなる地点を指し示してくれる起点となることだろう。テツラフは一歩一歩踏みしめながら歩いてゆく。Text:川田朔也