




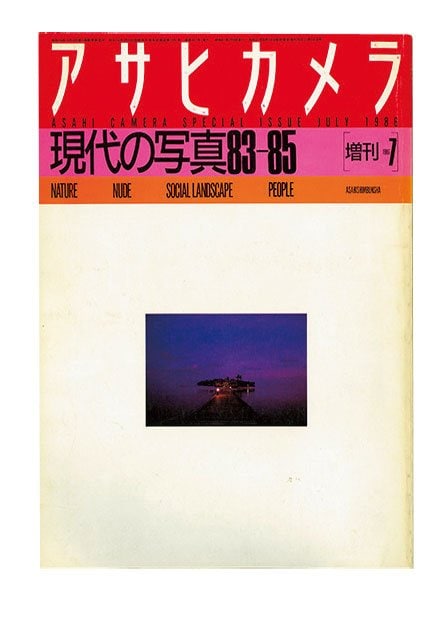
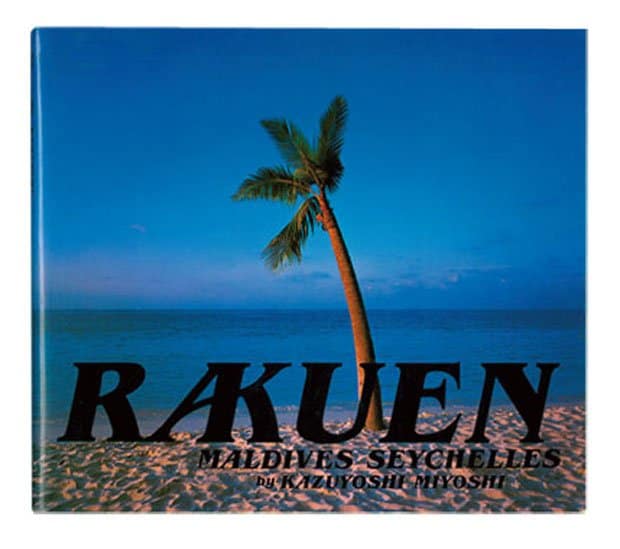
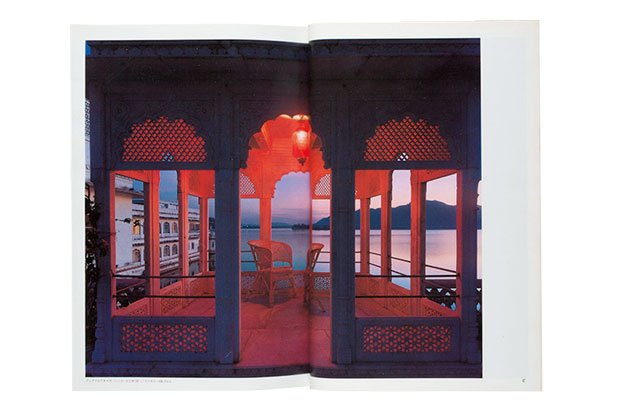


写真雑誌の危機感
1986(昭和61)年4月号で、本誌は創刊60年を迎えたが、それは心から喜べる還暦ではなかった。前号で触れたように部数の低下に苦しんでいたからで、その一因は、誌面づくりと読者のニーズとの齟齬(そご)にもあった。
同号の創刊記念特集に大辻清司が寄稿した「スタンダードな写真雑誌」は、本誌の戸惑いを端的に述べている。大辻は、かつての「アサヒカメラ」は写真ファンにとって中立公平で「円熟した教科書」だったが、いまやその役割は果たせなくなったとする。なぜなら写真表現が多様化し、「啓蒙や指導性は出る幕がなくなった」からだ。
表現の多様化は、これより2年前、84年の第9回木村伊兵衛写真賞(以下、木村賞)の「該当者なし」という結果にも表れていた。木村伊兵衛の没後10年にあたるこの年は、過去最多の31人が候補者として推薦されたが、ノミネーターからの最多の回答が「該当者なし」だったのだ。
4月号の選評によれば、それでも4人の選考委員(安部公房、石元泰博、渡辺義雄、相沢啓三編集長)は桑原史成「非武装地帯」、須田一成「関東風譚」、英隆「巴里神話」の3人に絞っている。だがいずれも決め手に欠けていた。しかも、めずらしく選考委員から、各作品への「批判的な見解が進んで表明された」のだった。
翌85年4月から編集長に就いた藤田雄三は、かつて本誌に在籍していただけに、その低迷ぶりに戸惑いを受けたという。
「久しぶりに古巣に戻ったとき写真界から聞かされたのは、一時期の誌面に対する『わからない』『暗い』という指摘、包み隠さずいえば非難の集中砲火であった。だれのための何のための雑誌だろう」(「朝日新聞出版局史」) さらに着任と同時に「カメラ毎日」(毎日新聞社)が4月号で廃刊したことも危機感を増大させた。同誌は60年代から写真表現の動向をリードしてきたが、本誌以上に深刻な部数減に陥っていた。さらに発行元の毎日新聞社自体が経営難で、その再建のために休刊が決まったのだった。このできごとは写真界に衝撃を与え、写真雑誌の在り方が議論された。
本誌85年5月号の座談会「話題の写真」では、三木淳が、写真雑誌には写真芸術を大切にする「ピクトリアル・ジャーナリズム」と「写真の普及」というふたつの方向性があると述べている。ただ前者の需要は少なく「写真界の底辺であるアマチュア」を開拓しなければ写真界自体が消滅するから、レベルを下げ「ホビー・マガジン」に立ち返ることを提案した。
とはいえ半世紀以上も写真家の重要な作品発表の場であり続け、写真界の芥川賞と呼ばれる木村賞を主催する本誌が、「ホビー・マガジン」に特化できるだろうか。
冒頭に挙げた大辻の文は、それでも「いまだ未熟を自覚する若い写真家のために、何事か応じる方策が必要なこともまた確かではないだろうか」という問いかけで結ばれている。それは編集長の藤田もまた感じていたことだった。
「写ルンです」の風景
「カメラ毎日」最終号の座談会レポート「眼の出来事」には、西井一夫編集長の、同誌廃刊は「カメラ雑誌」という文化現象が終わっていく先駆けだ、との発言が紹介されている。根拠は「一時代昔には、記念写真から芸術写真まで頂点を形成する価値体系があったが、今は写真は一つのメディアとして全く別の価値体系を持っている」からだ。
それは自動化される写真技術とその日常生活との密着から生まれた、写真メディアの新しい展開を指している。この展開はまだポルノチックな投稿写真誌のレベルにとどまっているが、やがてコミュニケーションと高度な表現の境界さえあいまいにさせていくだろう。
こうした流れをさらに加速させるカメラが、このころ相次いで登場した。その筆頭が、85年2月にミノルタから発売されたAF一眼レフカメラ「α-7000」で、まさに全自動カメラの名に値する製品だった。本誌では、まず3月号の「新製品テスト速報」で玉田勇が取り上げ、「このカメラを手にしたときのインパクトを、恐らく、生涯忘れることはないだろう」と書いた。4月号の「ニューフェース診断室」では「家庭の奥さんや初心者を対象に開発されている」が、じつはスポーツカメラマン向きともいえる性能を備えており「文句なしに、面白い一眼レフが誕生した」と絶賛している。
商業的にもα-7000は大成功を収め、7月号では、発売以来売り切れが続き「不況のカメラ業界をひさびさに活気づけた」と報じられている。本機の登場を皮切りに、翌86年にはニコンF-501、オリンパスOM-707、京セラ230-AF、87年にはキヤノンEOS-650などの新機種が発表され、メーカー間の競争は「AF戦争」とも称された。
とはいえ、カメラ市場の本当の主役はAF一眼レフではなく、安価だが十分な性能をもったコンパクトカメラに移っていた。それは84年に総出荷金額で一眼レフを追い越し、86年には1.5倍に、国内に限定すれば2.8倍にまで拡大していたのだ。
コンパクトカメラ以上に写真を身近にしたのは、86年7月に富士写真フイルム(現・富士フイルム)から発売された“レ
ンズ付きフィルム”「写ルンです」だった。小さな110フィルムを使用した24コマの使い切り、シャッター速度は100分の1秒でレンズはF11の固定焦点という簡素なスペック。用途は出張時の記録や子どもの遠足と運動会などが想定された。だがネーミングのよさもあって大ヒット商品となり、翌年には35ミリ判の「写ルンですHi」やフラッシュ付きが発売され、以降も多くのバリエーションが作られていく。
コンパクトカメラや「写ルンです」のヒットは若い女性層を含む、新しい写真ファンをつくるきっかけとなった。それは気軽な自己表現と友人間のコミュニケーションとしての新しい写真文化、西井の言う別の価値体系を育てる土壌となるのである。
また同時期には、磁気ディスクにアナログの画像データを記録する電子スチルカメラも誌面で話題になっている。電子カメラの嚆矢(こうし)は81年に発表されたソニーの試作機「マビカ」だが、市販されたのは86年7月発売のキヤノン「RC701」である。富士写真フイルム、小西六などのカメラメーカーのほか、カシオ、松下電器、シャープなどの電機メーカーも製品システムを発表したが、市場の反応は芳しくなかった。
この点について、87年8月号の「電子スチル写真の展望」で研究者の斎藤光範がふたつの理由を指摘した。それは30万前後の画素数では銀塩写真と比べてプリント時の画質が落ちること、そしてなにより「この写真システムを何に使用したらよいか」が誰にもわかっていないことである。後者の問題への回答は、まる10年後のインターネットの普及開始によってようやく出され、「全く別の価値体系」もさらに発展していくことになる。





































