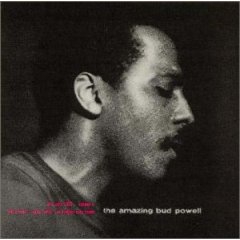
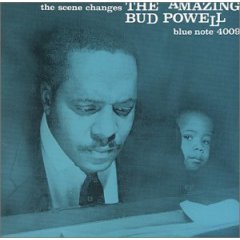
●パウエルの音楽がもつ“業”
天才の音楽はわかりにくい。天才の発想は凡人のありきたりな情緒のありようを超えているから、あらかじめ用意された聴き手の感情の引き出しにスンナリと収まらないのだ。だから活字の知識でパウエルを「モダン・ジャズ・ピアノの開祖」などと知ってはいても、愛聴盤となるには至らないという話をよく聞く。
私の場合は、ジャズを聴き始めたばかりの頃、たまたま周りに筋の良いパウエル・フリークが数人いたので、彼らによって有無を言わさずパウエルの演奏を身体に刷り込まれ、ずいぶん得をした。それでも『アメイジング・バド・パウエル第5集』(Blue Note)の有名曲《クレオパトラの夢》から、『アメイジング・バド・パウエル第1集』(Blue Note)に3テイクまとめて収録された《ウン・ポコ・ロコ》に至るには、かなりの時間を要したものだった。
それにしても興味深いのは、「クレオパトラ」から「ウン・ポコ」への過程は、そのままジャズ理解への道筋となっているところである。「ジャズに名演あって名曲なし」という至言があるが、その意味を実感したのはこうした曲によってだった。
日本人好みのマイナー・メロディ、パウエル自作の《クレオパトラの夢》は名曲といってよいだろう。誰でも一度聴けばロマンチックなタイトルともども、この曲想に魅了される。一方、同じくパウエルの自作曲ながら《ウン・ポコ・ロコ》は即物的というか、なにやら索漠とした印象の、とても名曲と呼べるようなシロモノではない。
ポップスの世界では明らかに勝負アリだ。ところがである、半ば強迫観念に取り憑かれるようにして《ウン・ポコ・ロコ》の3つのテイクを聴き比べたりするうち、知らぬ間にパウエルの魔界に引き込まれていた。深い。重い。
凡庸なミュージシャンが演奏したならばどうにもサマにならないであろうこの曲が、パウエルの手にかかると、聴き手をどうにも抜き差しなら無い状況に引きずり込むのである。まさに演奏の力というしかない。ジャズって面白いなあと実感した。
と同時に、ジャズって怖い音楽なのだということにも思いが至った。「ウン・ポコ」のなんとも無愛想な旋律の上っ面だけで、パウエルの音楽の言いようもない“業”に気がつかなかった私がいる。「クレオパトラ」のメロディだけで満足し、「演奏」というジャズにとって本質的部分を聴き逃していた自分がいる。
●経歴とその影響力
1924年、ニューヨークのミュージシャン一家に生れたアール“バド”パウエルは、ビ・バップ発祥の地とされる『ミントンズ・プレイ・ハウス』に出入りするうち、ハウス・ピアニスト(専属ピアニスト)のセロニアス・モンクに認められる。
40年代後半にはビ・バップ運動のスター、チャーリー・パーカーのコンボに参加、天才振りを発揮し、バップ・ピアノ奏法すなわちモダン・ジャズ・ピアノのスタイルを確立させるが、精神疾患の治療法に問題があり、時期によって演奏技術に好不調の波がある。しかし晩年パリに渡ってからの、技術に衰えが見えるといわれる演奏においても天才ならではの独自の世界を表現している。
彼の影響は絶大で、ウイントン・ケリーはじめトミー・フラナガン、ケニー・ドリュー、ソニー・クラークなど、50年代ピアニストの大半がパウエルのスタイルをコピーし、彼らは“パウエル派”などと呼ばれた。パウエルはまた、今では当たり前となっている、ピアノ、ベース、ドラムスによるピアノトリオのフォーマットを確立させた、ピアノ・トリオ・スタイルの創始者でもある。
『アメイジング・バド・パウエル第1集』(Blue Note)は、彼の絶頂期と言われた1949年から51年にかけてのピアノトリオ演奏、及び、バップ・トランペッターの大物ファッツ・ナヴァロとのセッションを収録した彼の代表作である。
【収録曲一覧】
『アメイジング・バド・パウエル第1集』(Blue Note)
1. ウン・ポコ・ロコ(テイク1)
2. ウン・ポコ・ロコ(テイク2)
3. ウン・ポコ・ロコ
4. 異教徒たちの踊り
5. 52丁目のテーマ
6. イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー
7. チュニジアの夜(別テイク)
8. チュニジアの夜
9. ウェイル
10. オーニソロジー
11. バウンシング・ウィズ・バド
12. パリジャン・ソロフェア
バド・パウエル:Bud Powell (allmusic.comへリンクします)
→ピアノ奏者/1924年9月27日 - 1966年7月31日


































