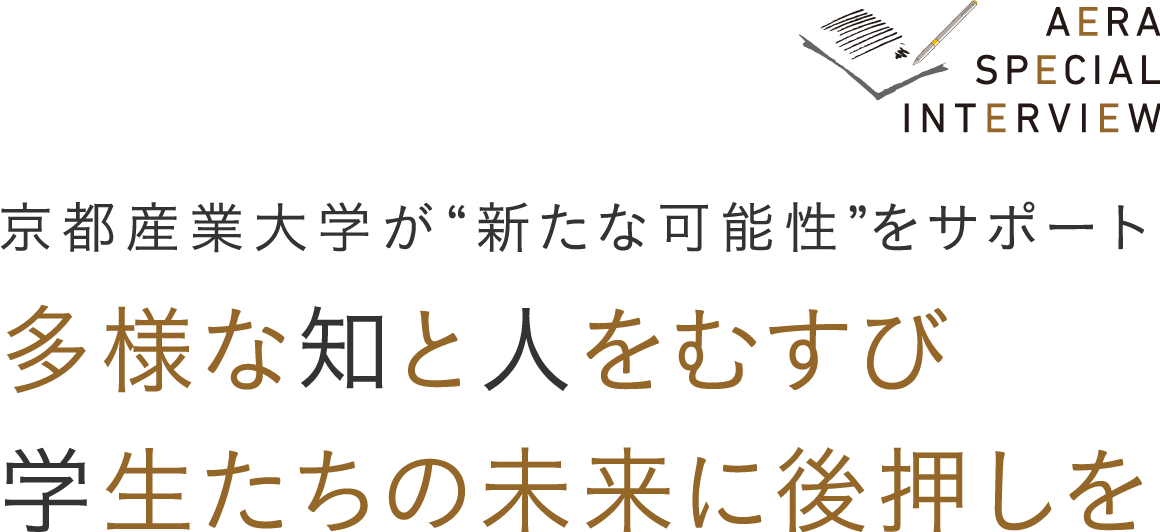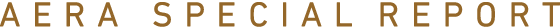Akira Kurosaka
黒坂 光さん
京都産業大学
学長
1957年生まれ、大阪市出身。薬学博士(京都大学)。1986年、京都産業大学国土利用開発研究所の講師に就任。以後、工学部生物工学科教授、総合生命科学部長、工学部長、副学長などを歴任。2020年10月から現職。
木村 今年度からアントレプレナー育成プログラムなどの取り組みが始まっていると伺いました。人材育成について今改めて注力している、その思いをまずは聞かせてください。
黒坂 本学では、「建学の精神」として「将来の社会を担って立つ人材の育成」を掲げています。その実現には今日の社会を的確にとらえ、将来に向かって人材育成をすることが大切だと考えています。これからの若い人たちが生きていく将来は、これまでの人たちが見てきた「将来」とは違いますから。そこを明確にして、大学の教職員がみんな同じ方向を見て運営を進めていきたいです。
木村 先行きが不透明な将来を見据えて人材を育成する難しさがあると思いますが、どういう人材が求められていると思われますか。
黒坂 これからの若い人たちが生きるのは、Society 5.0と言われるデジタルイノベーションの社会です。また、温暖化、食糧、ジェンダー、感染症など様々な社会課題がグローバル化していて、一つの専門分野の学びだけでは解決できません。例えば感染症の問題にしても、私は専門が薬学ですからウイルスのことはよくわかりますが、医療現場のこと、法律、人々の行動心理、社会科学的な視点なども問題解決には必要です。そういったことを認識して、学際的な感覚をもって課題解決できる人材を育てていきたいと考えています。
木村 新たな価値を生み出していくことができる人材、アントレプレナーシップがこれから重要なんですね。
黒坂 大学名が示すように、本学は開学時から産業界との連携を意識しています。1965年に天文学・宇宙物理学者の荒木俊馬が創設し、経済学部・理学部の2学部でスタートしました。一般的に産学連携が大きくうたわれ始めたのは90年代以降です。それまではむしろ大学は産学連携ではなく、アカデミズムの場でした。しかし、本学は大学ができた時から連携を志してきました。これからは単に産学を連携するだけではなく、新しいビジネスを創出できる学生の育成につなげたい。

Keiko Kimura
木村 恵子さん
AERA 編集長
木村 会社とか組織の中にいても同じことですよね。全員が起業家にならないとしても、そのマインドは絶対に必要だと実感します。
黒坂 家業を承継する学生も多いのですが、その場合も単に承継するのではなく、展開させていく力が必要です。
木村 具体的にはどういったカリキュラムになりますか。
黒坂 アントレプレナー育成支援に取り組んでいる大学は数多くありますが、多くの場合は、資金提供など最後の出口の部分でのサポートです。入り口の部分は自発的な学生の頑張りに任せるところが多い。本学のプログラムでは、1年生の時から正課教育として位置付け、全学部の教員が関わります。起業を志向する学生は情報、知識をしっかり学んだ上で実践に進んで、外部と接する機会を持ちますから、段階を踏んで準備していくことができます。
木村 地域の方や、すでに社会に出て活躍している人たちも巻き込んで、多種多様な連携をしていくと伺いました。すごく面白いし、学生にとっては貴重な学びになりますね。
黒坂 京都産業大学には卒業生が約16万人います。経営者もいるし、企業で優れた活躍をしている方もたくさんいる。年齢などの属性を問わず、そのネットワークをフル活用していくつもりです。
木村 大学に人材育成へつながる拠点があると心強いですし、いろんな刺激を受けて、さらに社会に還元できる。社会人になってもこの取り組みでの経験は、いいつながりになるのではと感じます。
木村 次に「大学DX」の取り組みについてお聞かせください。
黒坂 学長に就任して最初にDX推進の計画を文部科学省に申請し、補助事業の採択を受けました。学生の情報を統合してデータベース化し、それを元に教育を充実させる。学生の成長を可視化させていきたいと考えています。
木村 ソフトバンクやLINEヤフーなどの企業との連携も進めているとか。
黒坂 例えば、バスの待ち時間がリアルタイムでわかるとか、食堂の行列を解消するとか、「スマートキャンパス化」でいろんなことが可能になります。よくキャンパスが(京都の中心部から)遠いと言われるんですが(笑)、実際に来てみたらとても便利、という状態を作りたい。今年の学園祭(神山祭)では、模擬店でのキャッシュレス決済を可能にしました。
木村 それはすごい。教育面と環境面と、両面でDXを進めていくということなんですね。
黒坂 学生1万5千人がワンキャンパスに集まって学んでいますから、変化を取り入れたら、全学生がそれを享受できる。これも京都産業大学ならではの強みだと思っています。
木村 これからの時代のイノベーションというのは、理系は理系だけで、文系は文系だけで、というふうに分散していてできるものではなく、合わさって生み出されるもの。そういう点でもワンキャンパスは理想的な 環境ですね。色々お聞きしてきましたが、どれも、「むすんで、うみだす。」というスローガンで表現されている大学像がベースでつながっていると感じました。
黒坂 大学名である「産業」を、私たちは「むすびわざ」と読み解いています。新しい業(わざ)をむすび、新しいものを生み出す。教室の中の学びだけでなく、地域そして世界に飛び出し、産業界とも連携しながら外での学びを融合させて、新しい価値を生み出していく。京都は歴史と文化の街ですし、優れた先端企業も多くあります。
木村 おっしゃる通りですね。旧き良きものと、新しいものを融合するのに、まさに京都という場所は適しています。
黒坂 次の時代を切り開いてくれる若い力、人材を一人でも多く京都産業大学から輩出していきたい。新しいことにチャレンジしたい高校生の皆さんは、ぜひここにきて一緒に学んでいただきたいと思います。
木村恵子の編集後記
ワンキャンパス総合大学を掲げる京都産業大学。学長のお話から伝わってきたのは、社会で芽が出ていることをいち早く捉える先進性と、それを実現していくスピード感です。緑豊かで壮大なキャンパスを歩いてみて、多様なものが共鳴しあって大きな力になっていることを感じました。