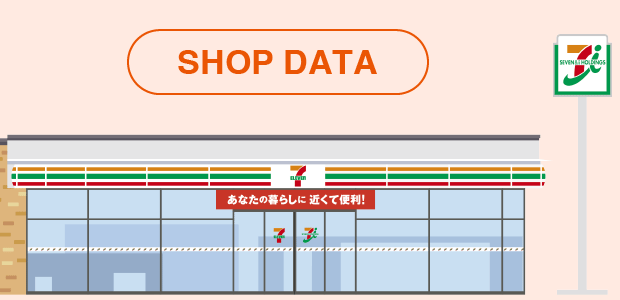二人とも北九州市門司区生まれ。政明さんは小中高大とサッカー漬けの日々を送り、現在は少年サッカーチームを率いる。征子さんもサッカーや水泳などの競技歴があり、運動が大好き
関門海峡に面した門司港は、日本の近代化を支えた港町の一つである。港の周囲には明治から昭和初期に建てられた建造物が数多く残り、現在では「門司港レトロ」として人気の観光スポットとなっている。このエリアから徒歩約10分のところに、セブン-イレブン門司港松本店はある。1981年に産声を上げた北九州市第1号店である。
店は古くからの住宅街にあり、お客様のほとんどが顔馴染み。シニア層が多く、「お体の具合はどうですか?」「ぼちぼちっちゃね」といったやり取りが、店のあちこちから聞こえてくる。従業員もベテランぞろいで、電話での配達注文に丁寧に確認を取りながら応対している。
「毎日来ていただく方も多く、日に何度も立ち寄られる方もいます。あいさつや話だけをしに来る方もいらっしゃいますよ。配達は一人暮らしの方が中心で、そのご家族からのご依頼も多いです」とオーナーの甲斐政明さんは話す。
門司港松本店は、政明さんの妻・征子さんの父であり、政明さんの義父である松本恭武さんが営んでいた酒店が前身である。
「酒店として会社形態にしたのが1930(昭和5)年。それ以前は、『諸式屋』と呼ばれる“何でも屋”でした。日用雑貨から食料品まで扱う、言ってみれば今のコンビニのようなもので、徐々にお酒の販売に特化していったと聞いています」と征子さんは言う。
酒店の商売は順調だった。しかし恭武さんは将来を見据えて、経営の勉強会などにしばしば足を運んでいたそうだ。
そんなとき、恭武さんのもとをセブン-イレブンの店舗開発担当者が訪ねてきた。その担当者は別の酒店での話がまとまらず、帰り道にたまたま目に入った酒店に飛び込んだということだった。
「この偶然がなかったら、今の店はなかったでしょうね。しかし、それもご縁。父はセブン-イレブンに可能性を感じ、家具店を営む親戚に相談したところ『日々の食べ物を扱うのはとてもいい商売だ』という後押しもあり、決心したそうです」
当時小学6年生だった征子さんは、オープン初日のことをよく覚えているという。「学校から帰ると、店の中が驚くほどたくさんの人であふれ返り、まるで満員電車のようでした(笑)」。
幼い征子さんも当時はレジの手伝いをよくしたという。
「楽しかったですね。本部から応援に来てくれた社員さんに『袋詰めがうまいね』と褒められたり。その頃、私を可愛がってくれたお客様は、今も変わらず見守ってくださっています」
隣町に住んでいた政明さんと征子さんは、学校こそ違うが高校時代からの知り合いだった。大学卒業後に勤めた会社で同僚となり、20代後半に結婚。郷里・門司に戻り、夫婦で店の運営に加わった。当時から政明さんは、ゆくゆくはオーナーを引き継ぐつもりだったという。
「以前勤めていた会社では発注業務にも携わっていたのですが、コンビニの仕事は初めてだから加減がわかりません。あるとき菓子パンの新商品を発注し過ぎたかと不安になり、義父に助言を求めると、『足りん!』のひと言。結局、倍の400個を発注したのですが、さすがに売れ残るのではと心配していたところ、あっという間に完売してしまい、驚きました」
豪快かつ先見の明も商売のセンスもある義父から、店内の業務を一つひとつ教わった。経営のことはゆっくり覚えていけばいい、時間はたっぷりある。そう思っていた。
ところが2年後の1998年6月4日、まだ54歳だった恭武さんが倒れた。

門司港松本店のオープン時。恭武さん夫婦をはじめ、家族総出で準備に取り組んだ。水玉模様のポップなユニフォームは第一世代のもの
「脳出血で、一命はとりとめたものの重症でした。これを機に、私がオーナーとして店のすべてを引き継がねばならなくなったのですが、税金や給与計算など、わからないことだらけ。ともかく、山積みになっていた手書き書類の“解読”から始めました」と政明さん。
征子さんも経営についてはわからず、当時は子どもが生まれたばかりで店に出ることもままならなかった。政明さんはまさに孤軍奮闘の状態で、店のシフトに入り、発注など慣れない業務に忙殺されていた。
その危機を支えてくれたのが、長く働いてくれている従業員さんたちだった。
「最初のうちは業務を全部自分で抱え込んでいました。しかし一人では無理だと気づき、従業員のみなさんに少しずつ業務をお願いするようにしたのです」
政明さんは経営業務に集中できるようになり、次第に店を円滑に運営していけるようになった。
そんな折、近隣に他のコンビニエンスストアがオープンし、近所のスーパーが深夜営業を開始したことなどもあって、苦戦を強いられるようになる。
「今は数台分を確保していますが、以前はまったく駐車スペースがなかったことも悩みの一つでした。車を使っているお客様にも安心してお店を利用していただきたいと思っていました」
そんなとき、念願だった2号店出店の話をもらった。2011年7月、門司港松本店から徒歩約10分のところに十分な駐車スペースのある門司東門司2丁目店をオープン。
「車で来店するお客様にも喜んでいただけました」
2号店開店の頃から、発注業務を細かく従業員さんに割り振るようになった。
「従業員さんたちには、それぞれの個性を生かしてもらうことを大切にしています」と政明さんは言う。
「市場の仲買人のような威勢のいい掛け声をかける人もいれば、カードゲームにめっぽう詳しい人もいる。それぞれが持つストロングポイントを生かし、ウィークポイントは他の人が補う。私は少年サッカーチームで子どもたちを指導しているのですが、店の業務もチームスポーツと同じだと思うんですよね。各自に適したポジションがあり、そこでそれぞれに力を発揮してもらう。これがまとまると、すごいパワーが生まれるんです」
配達がその一例だ。2012年に「セブンらくらくお届け便」の小型電気自動車が導入され、その担当をオープン当初から勤める誰よりも地域に詳しい従業員さんに任せた。するとこまめな訪問や気配りで、お客様から大きな支持を得ることができた。

先代の頃から約40年在籍する大嶋和幸さん(中)と、森田征幸さん(左)。
右は、40年以上勤めて昨年退職し、現在は長崎に住む浅野光男さん。
3人は“レジェンド3人衆”と呼ばれ、地域のお客様からも親しまれている

適材適所のチームプレーが功を奏し、門司港松本店は2013年度に、門司東門司2丁目店は2019年度に本部から「優秀店」として表彰されている。
「信用は少しずつしかつくれず、失うのは一瞬。地道にコツコツが一番」。義父の教えは今も大切にしている。それを端的に表しているのがおせちの販売だ。「店や配達時での声掛けもあってじわじわと数字が伸び、毎年ほとんどのお客様がリピートしてくださっています」
数年前、門司は大きな台風の直撃を受けた。激しい風で入り口上部の店頭看板が外れそうになり、政明さんは業者を待ちながら、脚立に乗って看板を押さえていた。すると通りかかった近所の工務店の主人がそれを見て、急いで応急処置を施してくれたという。
「ここはいい街なんですよ。優しい人ばかり。これからもずっと、みなさんが楽しく暮らせるお手伝いをしていきたいと思います」と政明さん。「『地域に貢献したい』というのは、父もよく言っていたことです」と征子さんも賛同する。
暴風雨の中、来店したお客様は、ほっとした表情でこんな言葉を掛けてくれたという。
「開いててよかった」
そしてあるときはこんな声ももらった。
「欲しいものがいつでも買えて、我が家の冷蔵庫として使っています」
政明さんは、セブン-イレブンが便利さとともに、安心を提供していることをあらためて実感したという。
訪れる人のほとんどが顔馴染みの店は、買い物の場であるのと同時に、地域の交流の場ともなっている。店では、買い物に来た客同士や、従業員との会話が絶えない。

お客様との会話を楽しむ小﨑千恵さん(右)と、カードゲームに詳しい自称“ちびっこ担当”の西川澪さん(左)。毎日来店するご近所さんと
お店だけでなく、配達は一人暮らしの人の安否確認の役割も担っている。家で倒れているところを発見し、救急車を呼んだこともあるという。
「セブン-イレブンは、いまや電気やガスと同じ、ライフラインの一つになっているのだと思います」
政明さんが少年サッカーチームの指導を続けているのも地域への思いが強いからだ。2年間コーチを務めていたチームが廃部になる際に、自らチームを立ち上げた。それから18年。チームのOBが高校生や大学生になり、従業員として店の戦力になってくれることもある。
従業員の年齢層は幅広く、勤務歴が長い人が多い。14年以上勤めている小﨑千恵さんは、高校生のお孫さんと一緒に働いている。「働きやすいお店だから安心です。私たちにとって、ここは地域の人と触れ合える大切な場所なんです」と小﨑さんは言う。
政明さんは今年、義父の恭武さんが倒れたときと同じ歳になった。後継のことも真剣に考えるようになった。
「セブン-イレブンの店名は通常、地名などで構成されることが多いですが、門司港松本店の『門司港』は地名ではなく、また、『松本』は酒店時代の屋号『松本商店』からとられています。義父から受け継いだ店と従業員さん、そして店に懸ける思いを、店舗名とともにこの地に残していきたい、いや、残していかなければと思っています」

![セブン-イレブン[50周年企画]明日の笑顔を 共に創る](./img/title-2.png)