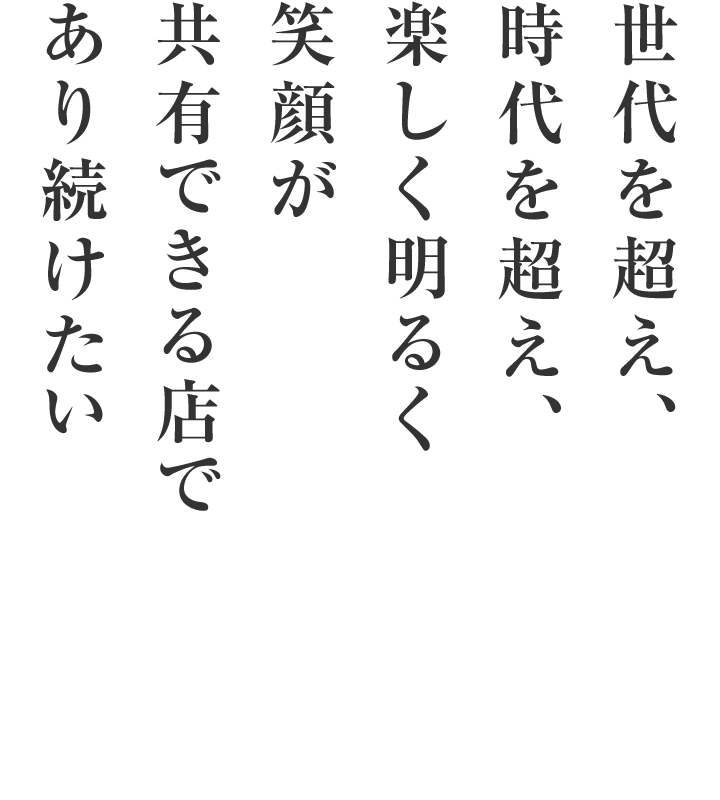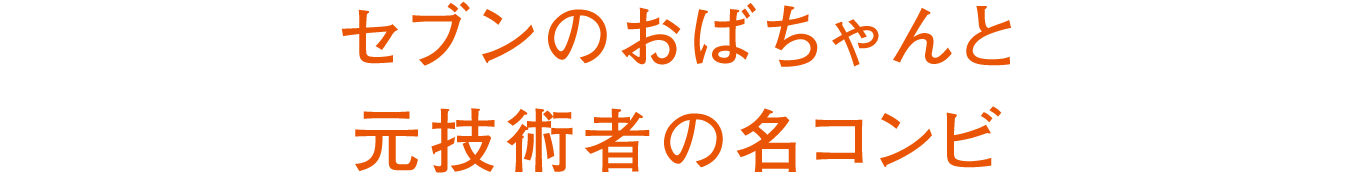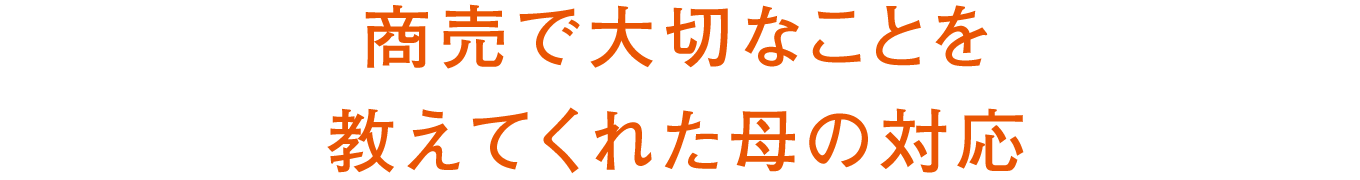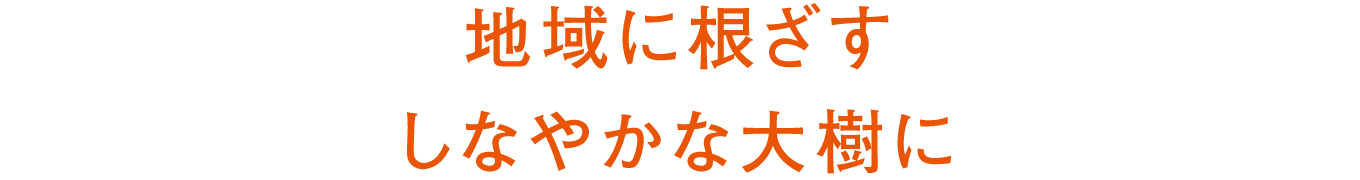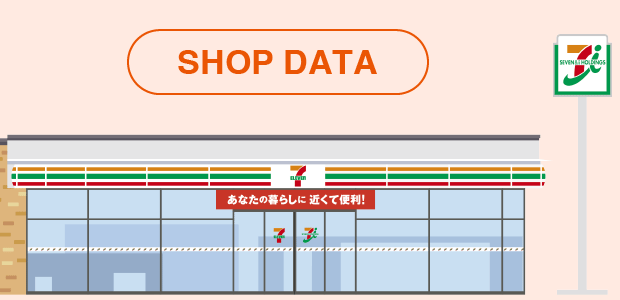趣味は「五感を磨くこと」。子どもたちへの読み聞かせを定期的に行っている。店舗数を拡大し、イートインスペースを設置できたら、「そこでお話会を開くのが夢」という
「セブン-イレブン宇都宮鶴田バイパス店には、子どもや学生のお客様もたくさんいらっしゃいます。その子たちがやがて大人になり、自分の子どもを連れてくる。そんなふうに世代を超えて利用してくれるお客様が多いんですよね」
にこやかにそう話してくれたのは、オーナーの清水博子さんだ。実は博子さん自身も、2代目オーナーである。先代の父・齊藤忠千代さんは、妻の南美栄さんと1984年、1号店の宇都宮鶴田三の沢店をオープンした。
セブン-イレブンへの加盟を強く推したのは南美栄さんのほうだった。忠千代さんの転勤にともない横浜から宇都宮に引っ越して来たとき、南美栄さんはたまたまセブン-イレブンのオーナー募集チラシを見た。
「本当は何年かしたら横浜に戻ることになっていたのですが、暮らすうちに『ここにずっといたい』と思うようになりました。そこで、宇都宮で生活するための術として、セブン-イレブンをやろうと考えたんです」と、南美栄さんは当時を振り返る。そして、こう続けた。「私は、やると言ったらやるんです(笑)」。セブン-イレブンの仕事は楽しそうだし、社会に必要とされる仕事だと、直感した。一方で、新しい世界に飛び込む不安もあった。
そこで南美栄さんはすぐに説明会に参加し、準備に入った。そして3回目の説明会のとき、それまで仕事で都合がつかなかった忠千代さんを初めて誘った。
「説明会に行くと、話の内容に将来性を感じ、加盟を決意しました。何しろ妻のやる気が強かったので、その気持ちに乗ることにしました」と忠千代さんは笑う。
当時、忠千代さんは自動車部品の会社に勤める熟練の技術者だった。セブン-イレブンを始めるにあたり、会社は辞めることにした。ところが、忠千代さんが培ってきた技術力は、簡単に誰かが取って代われるものではなく、当然のように忠千代さんは会社に慰留された。そこで忠千代さんは、自分の技術をしっかり後輩に引き継ぐことを約束し、会社の理解を得たという。
「長年にわたり身につけた技術を短期間で引き継ぐことは難しい。でも、お店の経営は初めてのことだし、夫婦二人で挑戦したいと思ったので必死に教えましたよ」
そうして、ようやく二人でセブン-イレブンを開店した。
南美栄さんの持ち前の才覚と忠千代さんの粘り強い行動力によって宇都宮鶴田三の沢店は軌道に乗り、やがて2007年には2号店となる宇都宮鶴田バイパス店を、2010年には宇都宮さつき店をオープンすることになる。
南美栄さんはお客様に対して積極的に、フレンドリーに接した。お客様が商品選びに迷っていると、やさしく声を掛けてあげる。そんな細やかな気遣いを重ねることで、南美栄さんはお客様一人ひとりの好みを把握していった。「あまり深入りするとご迷惑になることもあるので、そのへんはうまくバランスをとりながらね(笑)」いつの頃からか南美栄さんは『セブンのおばちゃん』と呼ばれ、地元で愛される存在になっていった。
「私の実家は商店だったので、子どもの頃から商売の様子を見ていたんです。だから、どうすればお客様が喜んでくれるのかが自然と体に染みついていたのかもしれませんね」と南美栄さんは話す。

節分に恵方巻を販売する際は、商品に付ける熨斗紙を毎回、神社で祈願している。写真は2009年当時の博子さん(左)、南美栄さん(右から2人目)、忠千代さん(右)
一方、セブン-イレブンを始めるまで技術者として数十年働き、商売の「し」の字も知らなかったという忠千代さんは、次第に商人としての経験を積んでいった。
「開店当時、私は夜の時間帯に店に入っていました。夜中にもいろいろな人が買い物に来ることを初めて知り、多くのお客様の役に立っていることを実感しました。あるときジェラートがすごく売れ、一気に数字が伸びたことがありました。商品が支持され、その結果、店の売上が伸びることを肌で感じ、うれしくなりました」と少し照れながら話してくれた。
それを横で聞いていた南美栄さんは、「普段はあまり話しませんが、お父さんは実は商売が大好きなんですよ」と大笑いした。
機微をとらえた二人の商いは、店を着実に成功へと導いていく。ある年はおでんの売上が好調で、テレビに取り上げられたこともある。
娘の博子さんは高校生のときに初めてアルバイトとして、セブン-イレブンで働いた。商品が売れれば、店の利益につながる。しかしそれ以上に、お客様が求めているものを提供することが、お客様の喜びにつながる、ということを知った。「二人が働く姿を見ながら、セブン-イレブンの仕事とは何かを学んだように思います」と博子さんは言う。
2011年3月11日、東日本大震災。
その日は宇都宮市でも震度6強の激しい揺れを観測、市内全域で長時間の停電が起き、負傷者や建物の損壊などの被害が出た。そんななか、3店舗は自家発電によってどうにか店を開くことができた。
「私が店の片付けを優先しようとしたら、母に『とにかく、裏にある食料品を全部お店に出しなさい。散らかっているところや危険な場所はお客様がけがをしないようにロープを張っておきなさい。片付けは後にして、まずはお客様のことを考え、商品を提供すること』と言われました。来店されたお客様からは、『セブン-イレブンが開いててよかった』『こういう状況でも商品が買えて安心した』という声をいただきました」
売り手良し、買い手良し、世間良し。
これはその昔、近江商人が商売の心得としていた「三方良し」の考え方で、「売り手の満足だけでなく、買い手も満足する。それに加えて、社会(世間)に貢献して初めて良い商売と言える」という意味だ。博子さんは大震災という非常時にあって、母がとっさに取った判断を通じ、商売の極意を体得したようだ。
「セブン-イレブンがこの場所にあることの大切さを、身をもって感じました」と、博子さんはしみじみと語る。
2020年1月、オーナーが、忠千代さんから娘の博子さんに交代した。博子さんの子育てが一段落し、お店を受け継ぐ覚悟ができたことが大きな理由だった。
とはいえ、忠千代さん、南美栄さんは完全に身を引いたわけではない。今でも裏方として陰になり日向になり、博子さんにアドバイスやフォローをし続けている。

買い物にきた女の子に声掛けをする従業員の境美穂さん。
菓子類は小さな子どもも見やすい低い位置に配置している
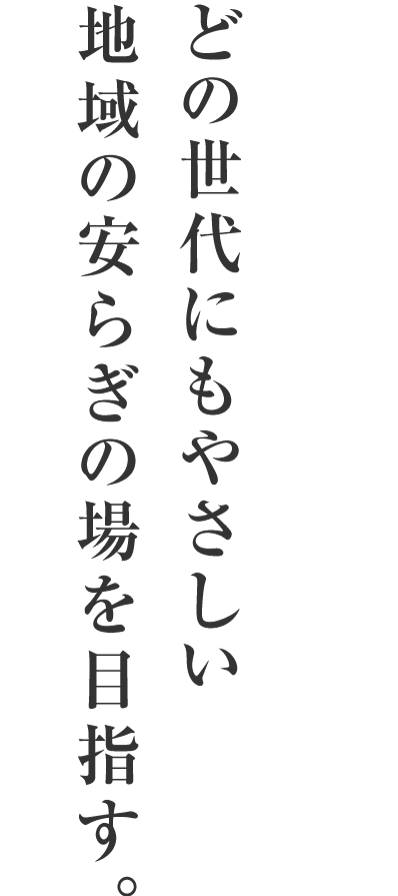
博子さんは、忠千代さん、南美栄さんが長年培ってきた商売のノウハウを受け継ぎつつ、オーナーとして自分なりのやり方を取り入れていった。その一つが「人財」である。
両親は何でも自分たちでできる人だった。その原動力は、お店を運営することの責任感と、仕事への熱い情熱である。これを自分自身が背負っていくことはもちろん大切だ。しかし、それをもっと多くの従業員に伝え、実行してもらうことが重要だと博子さんは考えた。
「私は学校を卒業後、百貨店で働いていたことがあるんです。そのとき人事部に所属していたこともあり、『人は財産』であるということ、そして、人を育てることの大切さを実感したのです」
博子さんは、両親がつくった“温かいセブン-イレブン”を残し、そして“セブンのおばちゃん”を受け継ぎ、さらに発展させ、近所の人が気軽に立ち寄りたくなる、昔の駄菓子屋さんのような店をつくっていきたいという。
「だから従業員さんたちには、『自分が想像する以上に、お客様に対してフレンドリーに接するように』と言っているんです。最初は恥ずかしい、という人もいますが、少しずつ、丁寧に教えています」

「活気ある店作りを心がけています」という従業員の別井しげるさん(左)と、「アットホームなこの店で働くことが楽しい」という加藤千恵さん
目標の店には、一歩一歩近づいている。宇都宮鶴田バイパス店の近くには私立高校がいくつかあり、学校への行き帰りに生徒が立ち寄っていく。まるでそれが日課のように、ごく自然な流れで。まさに学校と家をつなぐ“バイパス”のようだ。
子ども連れの母親に対しても、「お子さん、大きくなりましたね」などと自然に声を掛ける従業員さんが増えた。
「今日は(従業員の)おねえさんに会いに来たの」。母親と一緒に店にやってきた近所の女の子は、少し照れくさそうに話してくれた。母親に聞くと、「セブン-イレブンに行きたい」とよく言ってくるそうで、店は遊び場の一つとなっているようだ。大好きなお菓子を買ってもらい、楽しそうに、でも少し寂しそうに手を振りながら、帰って行った。
もちろん子どもたちだけでなく、高齢者にも気を配っている。
「お弁当をよく買っていかれるひとり暮らしの高齢者の方がいらっしゃるのですが、いつもと比べて元気がなさそうなときは、どこか悪くないですかと、声を掛けるようにしています」
博子さんは「みんなが笑顔でいてくれることが一番。お客様、従業員さん、お店に関わる人すべての人がそうあってほしいと願っています。みんなが笑顔でいてくれると、今日も良かったなと思う。みんなの笑顔が共有できる店であり続けたいと思っています」と話す。
そんな博子さんに、これからどんなお店を目指すのかをあらためて聞いた。
「大樹のように大きく根を張り、柳のようにしなやかに、時に木陰を作り休息の場となり、同じ場所に居続け、みんなのふるさとになれたらと思います」
地域に根差し、地域の人の拠り所となっている宇都宮鶴田バイパス店。これからもこの町に灯りを灯し続け、さらに大きな、頼りがいのある大樹に成長し続けていくことだろう。

![セブン-イレブン[50周年企画]明日の笑顔を 共に創る](./img/title-2.png)